
中世にキリスト教の三大聖地となり、今も多くの人を惹きつける「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」。歩くことで見えてきた「星に導かれた道」について、「まなぶ」「準備する」「旅する」「話す」の切り口で見つめ返した。
まずは「まなぶ編」で、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路とは一体何かを知るところからはじめよう。
Photo & Text : Mikito Morikawa
Index
6 min read
名前の由来と起源について
「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」という名前の「サンティアゴ」とは、イエス・キリストの十二使徒(キリスト教の成立発展に尽力した主要な弟子たち)の一人である聖ヤコブのこと。ヘブライ語では聖ヤコブだが、フランス語ではサン・ジャック、英語ではセント・ジェームズと、言語により呼び名はさまざま。日本ではスペイン語読みのサンティアゴという名称が定着している。
サンティアゴは、紀元44年に当時のユダヤ王に斬首され、十二使徒のなかで最初の殉教者となった。長い間、その亡骸は行方不明になっていたが、隠者ペラギウスが天使のお告げを受け、813年(814年という説も)に「星の光の導き」によって司教と信者が野原で墓を発見したといわれている。その場所が、現在のスペイン北西部の「コンポステーラ」だった(地名は、カンポ=野原、ステーラ=星という意味)。
サンティアゴの墓が発見されたのは、ちょうどイスラーム勢力がイベリア半島を圧倒していた時代。このコンポステーラは新たなキリスト教の聖地となったことで、レコンキスタ(再征服)とレポブラシオン(再入植)の最前線として、キリスト教を掲げる欧州の国の士気を高めることにもつながった。そうして、サンティアゴの聖地を目指す欧州諸国からの道が、「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」と呼ばれるようになったのだ。
12世紀には、年間約50万人もの巡礼者がサンティアゴの地を訪れたと伝えられているほど賑わっていたサンティアゴの巡礼路。その後、数百年にわたり下火になった時期もあるが、1986年にエリアス・バリーニャという神父が巡礼者のために道に黄色い矢印を描き始めたことをきっかけとしてスペイン各地で友の会が設立され、巡礼者数が徐々に増えていったといわれている。2023年には過去最高となる約44万人もの巡礼者数を記録。現在の巡礼者は国籍、年齢、宗教も多様で、歩く理由も、信仰だったり、自分探しだったり、友だちとの旅行だったりとさまざまだ。

サンティアゴ巡礼路をサイクリングしていたおじいちゃんと孫たち?巡礼路は地元の人にとっても大切な道だ。
巡礼路ってどんな道?
サンティアゴ巡礼路のルートは驚くほど多い(ルート詳細はNPO法人日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会を参照)。
もっともポピュラーなのが「フランス人の道」。サン・ジャン・ピエ・ド・ポーというフランスの街が出発点となっているためその名がついたが、ルートの大部分はスペインを通る。世界中から巡礼者が来ているため、雰囲気がインターナショナル。同じくさまざまな国の人が歩いている「ポルトガルの道」と同様、日本人にとってもなじみやすい。
逆に、フランスやイタリアを通るルートは巡礼者の大半がフランス人やイタリア人なので、その言語ができないと輪に入りづらいかもしれない。また、初めてサンティアゴ巡礼をしたアルフォンソ2世が歩いた「プリミティボの道」は、山間部の巡礼路になるためアップダウンが多く、距離は短いものの体力がより求められる。初めてであればまずはフランス人の道を歩いてみて、興味をもったら、それぞれ特徴がある別のルートにトライするのがおすすめだ。その頃には、サンティアゴ巡礼の沼にはまっているかもしれない。


フランスの道における最終日の風景。ラスト100kmを歩くと証明書がもらえるので、残り100km区間になると巡礼者の数が急増する。
日本との関係でいえば、四国の八十八カ所霊場を巡礼するお遍路や熊野古道に興味をもっている人も多く、私自身もサンティアゴ巡礼をしている間にそれらの道を歩いたことがある巡礼者に会った。また、お遍路や熊野古道と姉妹関係を結んでいる街もある。サンティアゴの巡礼路を歩いた証明書を持参して熊野古道やお遍路を完歩すると、二重、三重の証明書を発行してくれるので、3つの巡礼路を歩き通して巡礼路マスターを目指すのもありだ。

2015年、四国巡礼とサンティアゴ巡礼は協力協定を結んだ。また、和歌山県とスペインのガリシア州は、熊野古道とサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼道を姉妹道にしようと1998年に協力協定を結んでいる。

青と黄色が目印のサインは、フランスの道に限らず、ヨーロッパのさまざまな場所に存在し、巡礼路の行先を伝えている。
巡礼路のゴールは?
サンティアゴの墓が発見されたスペインのガリシア州ア・コルーニャ県のサンティアゴ・デ・コンポステーラには、現在、「サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂」が建っている。ここが巡礼者の最終目的地。大聖堂前の広場は、歓喜と安堵に包まれた巡礼者で溢れかえり、唯一無二の雰囲気がある。このサンティアゴ・デ・コンポステーラは、1985年に街自体が世界遺産に登録されている。ちなみに、1993年にはスペイン国内の「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」が世界遺産に登録され、1998年には「フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」も別途登録された。

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂は、1060年に着工され、1211年に基本的な構造が完成した。その後も建築がつづき、バロック様式、新古典主義様式を建物に見ることができる。
巡礼路が生んだカルチャー
サンティアゴ巡礼は多くの人を惹きつけるだけでなく、数々のカルチャーを生み出してきた道でもある。「まなぶ編」の最後は、先人たちが残したサンティアゴ巡礼にまつわる作品をみていこう。きっと旅の参考にもなるはずだ。
『人生に疲れたらスペイン巡礼 飲み、食べ、歩く800キロの旅』
小野美由紀・著
当時21歳の「人生に疲れていた」小野さんが、サンティアゴ巡礼路を通して何を感じ、何を発見したのかが書かれた旅エッセイ。人生の悩みを抱えている人にとって共感ポイントが多いはず。多彩な作品を生み出している小野さんの作家としての出発点がサンティアゴ巡礼にあったことは、巡礼旅がもつパワーを端的に表している。
『星の旅人 スペイン「奥の細道」』
黛まどか・著
俳人として長く活躍を続ける黛さんは「歩く人」としても知られ、お遍路をはじめ国内外の巡礼路を歩いてきた。そんな黛さんが20年以上前にサンティアゴ巡礼路を歩いたときの記録。今ほど知られていなかった巡礼路の当時の雰囲気を知ることができ、旅仲間との出会いと別れこそ巡礼路の一番の宝物だと教えてくれる。現在の巡礼者はスマホで撮った写真をSNSで共有するのが主な表現手段だが、絵を描いたり、俳句や短歌を読んだり、日記を書いたり、アナログな方法で自分と向き合うのも素敵だ。
『星の巡礼』
パウロ・コエーリョ・著
170カ国以上で出版されたベストセラー『アルケミスト 夢を旅した少年』で知られる、ブラジルの作家パウロ・コエーリョが書いた初めての小説。サンティアゴにまつわる物語をニューエイジの文脈で描いた自分探しの冒険譚に出合い、巡礼路を歩こうと決めた旅人は今も後を絶たない。本書を読んだ後なら、巡礼先で訪れる先々の街や道が新しい姿で立ち上ってくるだろう。
Profile
編集者
森川幹人(もりかわ・みきと)
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

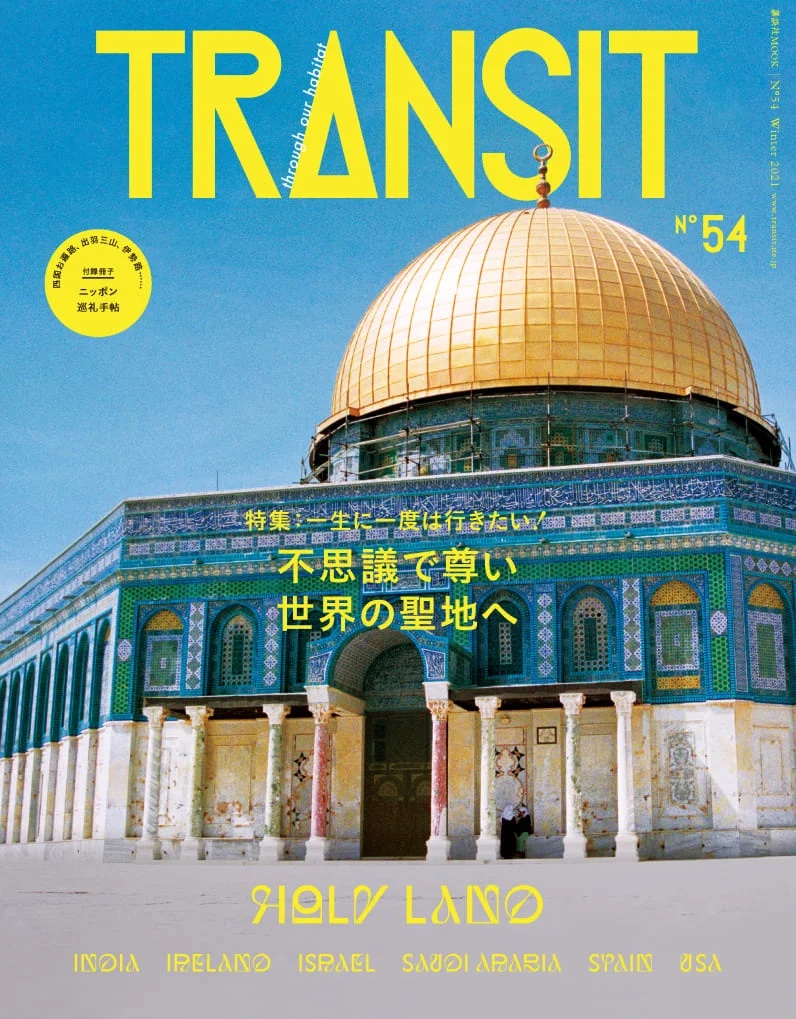









-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























