
中世にキリスト教の三大聖地となり、今も多くの人を惹きつける「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」。歩くことで見えてきた「星に導かれた道」について、「まなぶ」「準備する」「旅する」「話す」の切り口で見つめ返した。
「旅する編」では、実際にサンティアゴ巡礼をしているときに気がついた、長く歩くためのコツ、宿情報、食べ物……などをお届けします。
Photo & Text : Mikito Morikawa
Index
12 min read
◎食べる×巡礼旅
フランス、ポルトガル、スペインなどの美食の国を歩きつづけるサンティアゴ巡礼で、旅の疲れを癒やして元気を与えてくれるのが食の存在だ。朝昼晩で見ていこう。
●朝食
アルベルゲで有料もしくは無料で朝食が出る場合もあるが、メニューはパン、コーヒー、紅茶、ジャムなどのシンプルなもの。朝出発して1、2時間歩いてから、通過する街にあるバル(軽食、コーヒー、お酒などをオーダーできるスペイン旅に欠かせない店)でサンドイッチ、スパニッシュオムレツ、バナナなどを食べる人も。

バルで飲み物をオーダーすると一品おかずがついてくることも多い。普段はほとんど飲まないコーラだが、巡礼旅の間はほぼ毎日のようにがぶ飲みしていた。
●昼食
朝食と似たりよったりで、バルでスパニッシュオムレツやサンドイッチなどを食べて過ごしていた。街の広場には、ベンチ、水飲み場、ゴミ箱があるので、スーパーで買って食べると節約できる。日中は日差しが強いためか食欲がわかないこともあり、果物、飲み物、スナック、ナッツなどで済ませる場合も。ただ、重い荷物を背負って歩くためカロリー消費は多く、炭水化物やタンパク質はしっかり取ったほうがよい。
●夕食
大別すると、レストランで食べるか、アルベルゲ(巡礼宿)*が食事を提供している場合はそこで食べるか、アルベルゲにキッチンがある場合はスーパーで食材を買って調理するか。レストランでは巡礼者のためのメニューが12〜15€ほどで提供されていることもある。アルベルゲだと宿の世話人(ホスピタレーロ)がシンプルだが家庭的な料理をつくってくれることが多く、巡礼者たちとテーブルを囲んで食べるので交流の機会にもなる。また、多くのアルベルゲにはキッチンがあるので自炊すれば節約できる。自炊した料理をほかの巡礼者と分け合うことも頻繁に見かける光景。
*アルベルゲ……主に巡礼者が利用する宿。自治体や教会が運営する公営のものと、個人が運営する民営がある。

アルベルゲで夕食をいただくときは、ほかの巡礼者とテーブルを囲んで、一期一会の会話を楽しむ。みんなオープンでさまざまな話を聞けるのもこの旅ならでは。

レストランでの巡礼者用メニューは、スターターでサラダ、スープ、パスタなどから1品、メインで肉、魚から1品、ドリンクはワイン、水などから1つ、最後にデザートがつくのが基本的なパターン。スペインは野菜も新鮮で、ビタミン補給の観点でもありがたい。

ガリシア名物のタコ。茹でてオリーブオイルと塩をかけただけのシンプルな料理だが、とてもやわらかくビールのつまみに最高!
◎寝る×巡礼旅
多くの巡礼者が寝泊まりするのは「アルベルゲ(Albergue)」と呼ばれる巡礼宿。多くはドミトリーで、一つの空間に多くのベッドが並ぶ。料金は良心的で、10〜15ユーロほどが多く、寄付制のところも。設備としては、お湯が出るシャワーとトイレがあり、多くの場所ではキッチンや洗濯できるスペースがある。公営と私営があって、公営のほうが料金は安く、施設も質素なことが多い。また、スペイン語のサイトになるが、gronze.comというサイトはアルベルゲに関する詳細な情報を入手できる。

モリーナセカにある〈Albergue Santa Marina〉という宿は、オーナーが元巡礼者なので、バックパックを置けるボックスをはじめ旅人目線でデザインされた快適なアルベルゲで大人気。
アルベルゲのチェックインはだいたい14時以降、門限は夜10時前後に設定されていることが多く、チェックアウトは朝8時、9時など早め。田舎の街に滞在しているときは夜に満天の星空を見るチャンスなので、宿の管理人と交渉して1時間ほど外出する巡礼者もいた。「星に導かれた道」といわれるサンティアゴ巡礼路の途上で、天の川を見上げながら星を道標にして歩いたかつての巡礼者に思いを馳せても!

アルベルゲがオープンする前に到着した巡礼者がバッグを置いて場所取りをしている。ハイシーズンや混み合う街で宿を探す場合は、早めにたどり着かないと宿が埋まってしまうこともある。
アルベルゲは休むだけでなく、食事や団らんを通してほかの巡礼者や宿を運営するスタッフと交流し、さまざまなことを学べる場でもある。なかには古い修道院や城を改装したアルベルゲなどもあり、巡礼者だからこそ経験できることも多い。

ロンセスバリエスのアルベルゲは古い修道院を改装した大型の宿。スタッフは全員がオランダ人のボランティア。2週間にわたりボランティアとして巡礼旅を支え、2週間が経つと新しいボランティアとバトンタッチ。みんな元巡礼者で恩返しがしたいとボランティアとして働いている。
たとえば、キリスト教関係者が運営するアルベルゲでは、夕方に集会が開かれて、みんなで歌を歌ったり、巡礼路を歩いている理由を共有する機会がある。教会関係のアルベルゲでは、朝食や夕食が無料で振る舞われることも。
正直にいうと、これまで教会関係者のありあまる善意や親切を受けるとお腹いっぱいになってしまい、距離を置きたくなることもあった。ただ、巡礼路を歩いているときは、喉の乾きを感じたり、ふらふらの状態で巡礼宿に着いたりすることは日常茶飯事。そんなときに教会関係者や、かつて巡礼路を歩き、その恩返しをしたいというボランティアのサポートを受けると、切実さゆえに自然に感謝の気持ちを覚えることが多かった。
巡礼者は、サンティアゴの巡礼路をサポートしている多くの人の善意を受けているためか、自然に他者を助けたり手伝うようになる。まさに、キリスト教が伝える隣人愛の精神がリアルに存在しているのを感じた。

カリオンで宿泊した〈Hostel Parish Santa Maria del Camino〉というアルベルゲでは、シスターが集会を催していた。その後は、夕食が供され、巡礼者同士で夜更けまで交流する人も。
アルベルゲ以外の選択肢として、それなりの規模の街であればホテルもある。疲れが溜まって一人でゆっくり休みたいときはホテルに宿泊するなど使い分けするといい。歴史的な建物を高級な宿泊施設に改装したパラドールに泊まるのも選択肢の一つ。値段は五つ星ホテル並みだけれど、宿泊すれば一生の思い出になるのは間違いない!

レオンにある〈Parador de LEON〉は、16世紀に建設が始まり、2世紀かけて建造された病院兼修道院を改装した高級ホテル。スペイン中のパラドールのなかでも随一の豪華さ。
◎治す×巡礼旅
巡礼旅でのトラブルといえば、心配なのが身体の故障。もっとも多い怪我は、足にできるマメと膝の関節痛。足のマメを対策するには、自分に合った靴を履くこと、歩く前にマメ防止のクリームを塗ること、靴の中が蒸れるのを防ぐために頻繁に靴や靴下を脱ぐことや、靴下を途中で履き替えることなどがある。

足にマメができてしまったときは、清潔な安全ピンなどで豆に穴を開けて溜まった水を抜き、なるべく清潔さを保つことを心がけよう。マメができた部分を保護するシールなども売っている。
膝の痛みはよりやっかいで、症状がひどいときは数日休んだり、リタイアにつながることもあるので注意が必要。とくにフランス人の道は全行程のなかでピレネーの山を超える最初のステージがもっともきつい。体が疲れていないのでスピードは出るけれど、体は長距離を歩くことにまだ慣れていないため、関節を痛めてしまうことが多い。自分の体を観察して対話しながら歩くことが重要。とりわけ、山道では上り下りで膝への負担が大きくなるためポールを上手く使って怪我のリスクを最小限にしよう。

フランス人の道の初日で挑むことになるピレネーの山越え。登っているときは息も絶え絶えだが、後ろを振り返って見える絶景は筆舌に尽くしがたい美しさ。もといた場所を遠く下に見渡すと歩くことの偉大さを実感する。
◎祈る×巡礼旅
巡礼路の途上では多くの街や集落を通過する。大きな街もあれば、小さな村もあるが、どんな小さな集落にも、その中心に教会がある。カトリック(スペインはカトリックの国)の教会では、祭壇はきらびやかに装飾され、イエスの物語を伝える宗教画も掲げられ、プロテスタントの教会に比べて華やかな印象。大航海時代に世界の覇権国となったスペインの栄華が、何百年経った今も教会に息づいている。

「レオン大聖堂」は入場料が必要だが、歴史的な経緯なども詳しく紹介してくれるオーディオガイドつきなので、一見の価値あり。設計ミスで一時は倒壊の危機にあったが、なんとか修復して事なきを得たという切実なエピソードなど、小ネタを知ると意外とおもしろい。
毎日ミサが行われる教会も多く、地元の高齢者にとっては生活の拠り所となっていることを感じる。ミサは宗教に関係なく参加が歓迎されている。夕方に行われることもあり、所要時間は1時間ほどなので巡礼者も参加しやすい。巡礼者に対しては、通常のミサの後に神父が特別に祝福してくれる。

「ブルゴス大聖堂」はゴシック様式の教会。三角形に近い半円の天井が発明されたことで、それ以前に主流だったロマネスク様式の教会よりも壁が薄く、建物が高いのが特徴で、この大聖堂にもその様式がよく現れている。とりわけ豪華な祭壇は訪れるものを圧倒する迫力がある。

大切な故人のメモリアルのために備えられた十字架は途上で何度も見かけた。巡礼路は生と死をいつもより近くに感じる場所でもある。
◎巡礼の3つのステージ
サンティアゴ巡礼路を旅していて、ほかにはない旅の感覚を抱いていた。それを私なりに3つのステージに分けてまとめてみる。
ステージ1……「友だちづくり」
サンティアゴ巡礼は多くの巡礼者や巡礼路を支えてくれる人との出会いに満ちていて、長い巡礼旅をするうえで友だちづくりは大切な要素。とくに、歩き始めて間もない時期はみんなオープンなので友だちをつくりやすい。
巡礼旅における友だちは、終始一緒にいる関係を意味しない。巡礼者の多くはソーシャライジングと自分と向き合うことのバランスを上手く取っている。個人として自立したオープンマインドな人が多く、特定の仲間とだけつるむ人はあまりいないので、適度な距離感を保ちつつ心地よい友だちづくりがしやすい。

居心地のよさそうなバーやレストランを見つけると、巡礼者たちが三々五々集まってきて、小休憩する。
友だちをつくるために大切なことは、挨拶すること、笑顔を見せること、相手の名前を覚えること。どれもシンプルだが人間関係における基本のキ。巡礼旅の後に続く人生においても欠かせないことなので、せっかくの機会に輪の中へ飛び込んでみたい。
巡礼路で使われる言語は、スペイン語と英語がメイン。地元の人とコミュニケーションする場合、英語が流暢な人もそうでない人もいるが、片言でもスペイン語を話すと距離がいっきに縮まる。また、地元スペインからの巡礼者が多く、イタリア人、ポルトガル人をはじめとしてスペイン語が堪能な人も多いので、巧拙に関わらずスペイン語でコミュニケーションすると巡礼旅で見える世界はより深まる。
スペイン語圏以外の巡礼者における共通語は英語。全ルートを歩く場合は5週間というまとまった時間を過ごすことになるので、英語を上達させたり、英語圏のコミュニケーションスタイルを知るには絶好の機会。また、巡礼路では料理をしたり、歩いたりと言葉以外でお互いを理解するチャンスも多いので、英語が得意でない人にとっても巡礼者同士でコミュニケーションする敷居は低い。
話すのが苦手、外国語が苦手という人も使える、巡礼旅の魔法の言葉も紹介しておこう。
それが「Buen Camino(ブエン・カミーノ)」という挨拶。「良い巡礼を!」という意味で、巡礼中にすれ違ったり、別れのときに交わすことによって、巡礼者同士のコミュニケーションが始まり、つながりが生まれる。サンティアゴ巡礼路という目には見えないコミュニティに参加するために欠かせないマジックワードだ。

レリエゴスという小さな街の広場でカードゲームに興じていた地元のご婦人たち。巡礼者のなかにも簡単なボードゲームを持参してゲームを楽しんでいるものもいた。
ステージ2……「自分と向き合う」
旅の出発地となるサン・ジャン・ピエ・ド・ポーからブルゴスまでは、多くの友だちをつくり、いろんな話をしながらソーシャライジングを楽しむステージ。ブルゴスからレオンまでは、平坦な道が続くメセタと呼ばれる乾燥した高原に入る。ここまで来ると、それぞれのペースで歩いた結果、最初に出会った友だちとだんだん離れ離れになる。また、道に変化が乏しいため、景色に目を奪われることも少なく、登山道などと違ってそれほど用心深く歩く必要もないので、物思いにふけったり、自分と向き合うのにちょうどいい。
巡礼旅のいいところは、歩きながら考えられること。ただ頭のなかで考えるよりも、歩くというフィジカルな行動をしているときのほうが、いいアイデアが思い浮かんだり、これまで答えが出なかった問題に関して納得できる答えをすっと見つけられることも多く、身体と精神が密接につながっていることを体感する。
せっかくできた仲間とばらばらになるのは寂しいところもあるが、自分と向き合ったり、新しい人と出会うチャンスでもある。一人になることを避けたいがために、別の人のペースに無理に合わせていると、肉体的にも精神的にバランスを崩すことも多い。他者と交流することと自分と向き合うことのバランスを取ることが、巡礼旅を楽しむための秘訣なのかも。

自分に向き合う方法として、絵を描いたり日記を書く巡礼者もいた。
ステージ3……「巡礼後の道行きを考える」
旅する理由や時間の長さはさまざまだが、これまでの生活に一旦区切りをつけたり、今一度自分と向き合うために巡礼旅をする人は多い。ただ、巡礼旅をずっと続けることはできない。メセタのエリアを過ぎると残りは300kmほどで、旅の終わりがだんだん見えてくる。

巡礼者はそれぞれの願いや祈りを込めて石を積んでいく。その山は、長い時間の流れのなかで多くの人の思いが交差した証でもある。
サンティアゴ巡礼での時間や経験が自分にとってどんな意味をもつのか、巡礼旅を終えた後にどんなことをしたいのかあらためて考えてみるのもいい。明確な答えが見つかることは稀かもしれないが、歩きながら考えるという営みにこそ意味があるのかもしれない。そして、自分にとっての答えは旅を終え時間が経ってから見えてくることもあるだろう。
Profile
編集者
森川幹人(もりかわ・みきと)
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

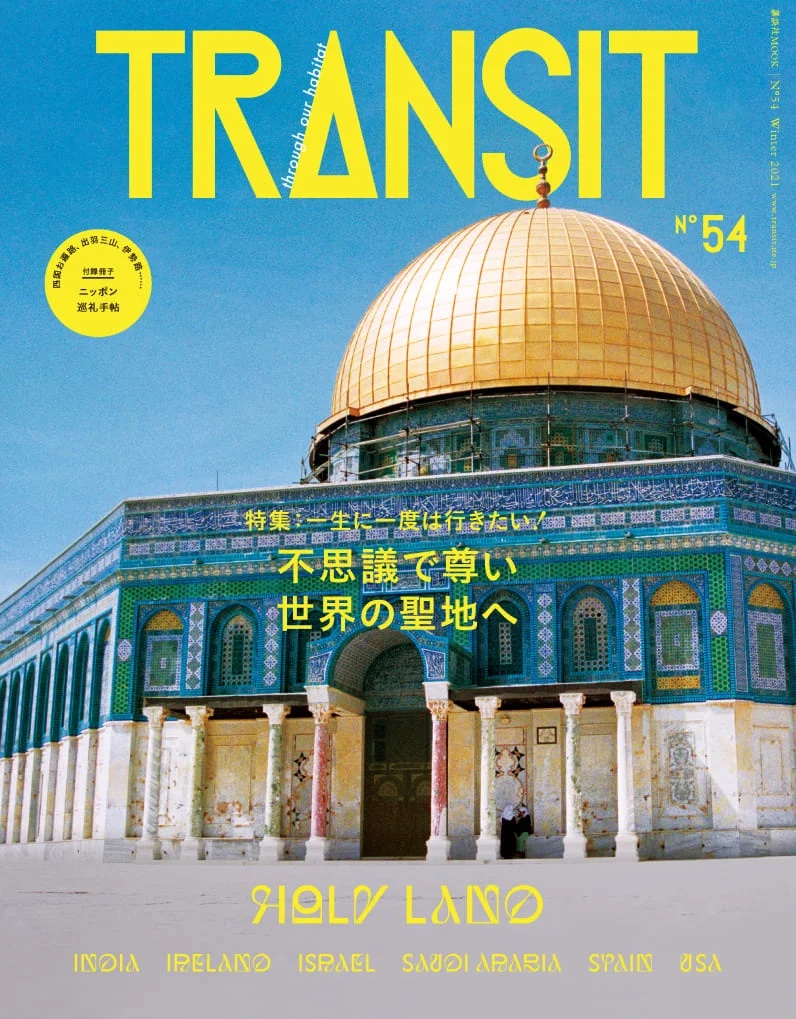








-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























