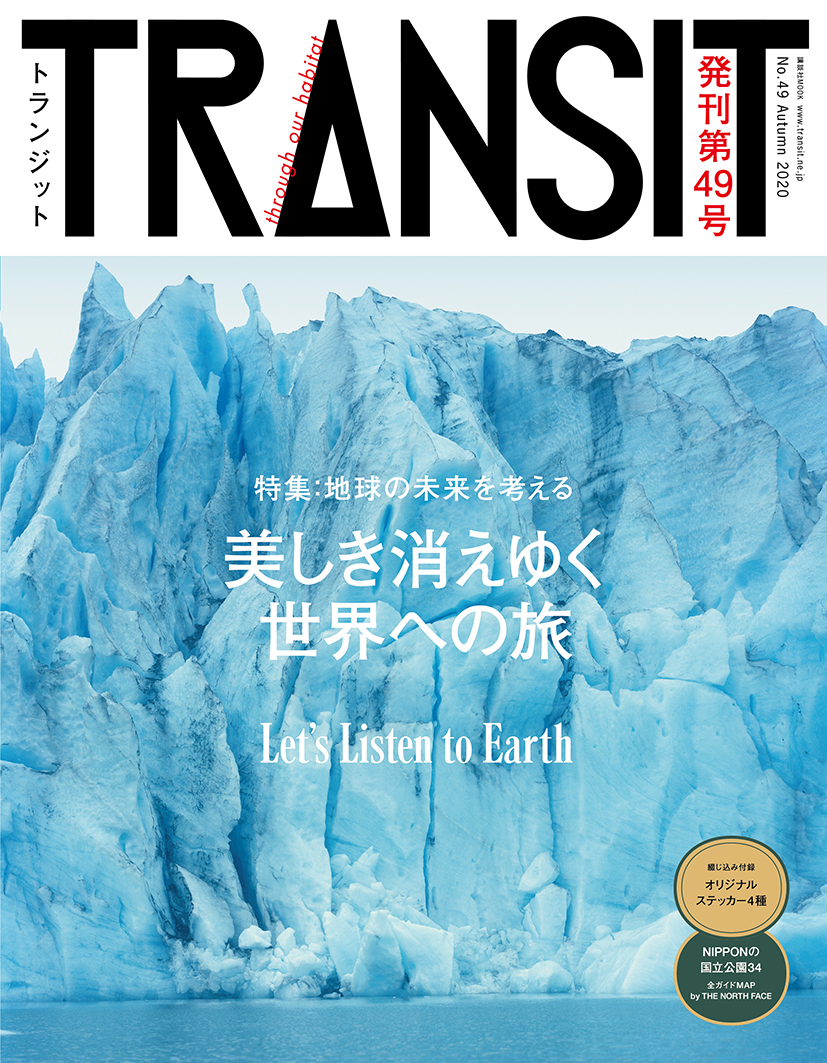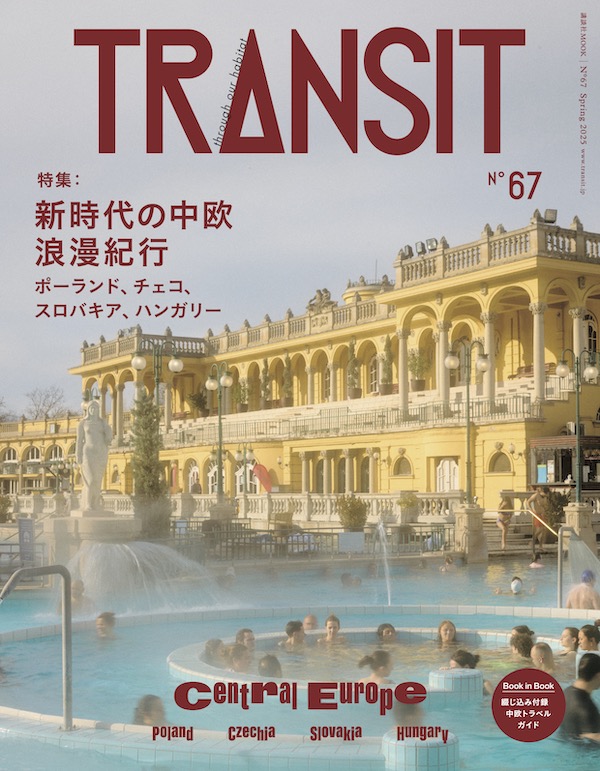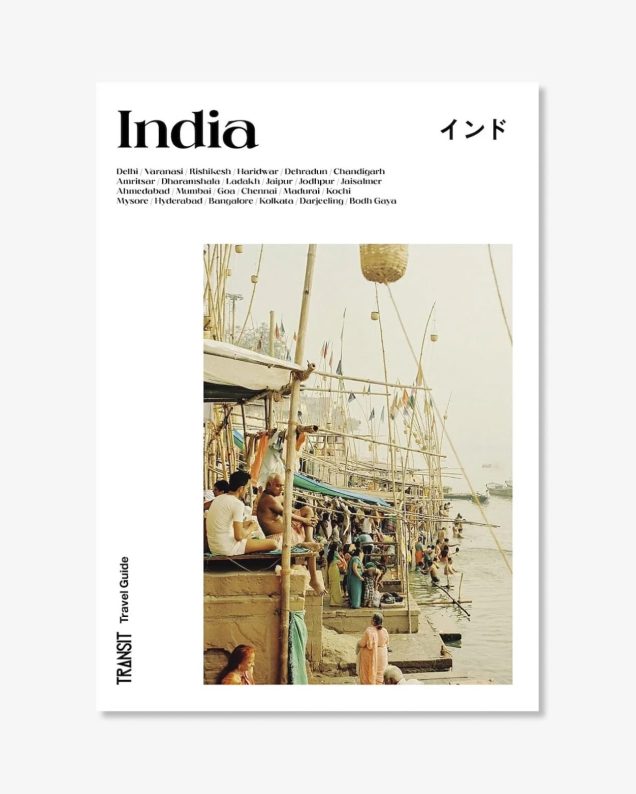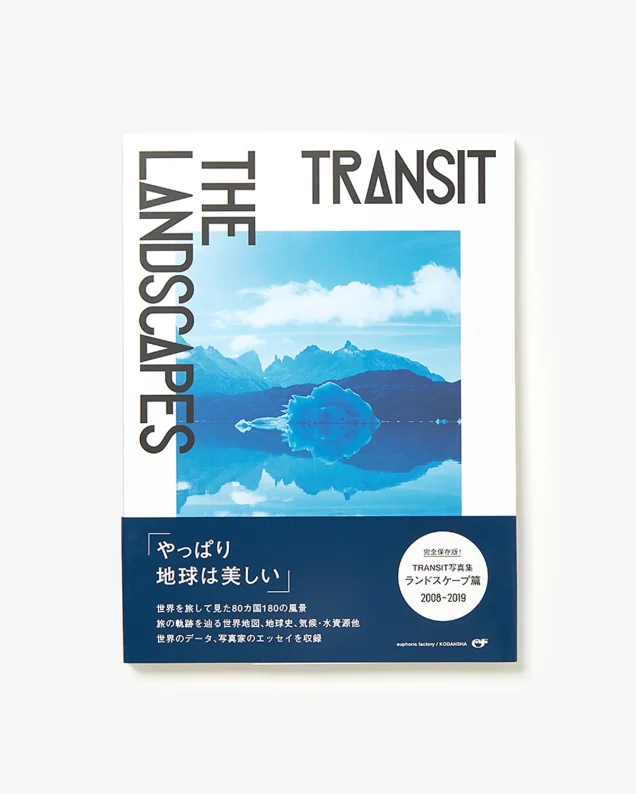地球がつくり出す、力強くて、神秘的な風景の数々。私たちは旅先で出合う風景とともに旅を記憶し、そしてまだ見ぬ風景を求めて次の旅に出る。生きている間に見たいと思っていたあの風景が、あと数十年、もしかすると数年で失われてしまうかもしれない。
失いたくない世界の風景を、ここに集めた。
Text:TRANSIT
1. ビクトリアフォールズ(ジンバブエ/ザンビア)
ビクトリアフォールズは、アフリカ南部のジンバブエとザンビアの国境にある、幅2㎞、高さ108mの大瀑布。南アフリカにあるイグアスの滝と並ぶ世界最大規模の滝だ。現地では古くから「モシオトゥニャ(雷鳴の轟く水煙)」と呼ばれており、ビクトリアの名がついたのはスコットランド人探検家、デイヴィッド・リヴィングストンにより発見された19世紀なかばごろ。当時のイギリス女王、ビクトリアにちなんでつけられたとされている。
この滝が繋がるザンベジ川は、ザンビア北部を水源にインド洋のモザンビーク海峡に注ぐアフリカ第4の大河。ビクトリアフォールズの水量は季節や年によって変動するが、2019年はアフリカ南部が最大の干ばつに見舞われたため、滝の勢いが弱まって枯渇が心配された。農業にも深刻な打撃を受け、食糧不足が問題に。穀物の生産量は前年比でジンバブエは53%、ジンバブエは15%減少し、それぞれ360万人と230万人が深刻な食糧不足に陥った。
ちなみに、今年は打って変わってビクトリアフォールズの水量は多くなっているが、干ばつは今後またいつアフリカを襲ってもおかしくない。アフリカは人口増加率が高く、農地の拡大にともない森林伐採が拡大している。森林はCO2などの温室効果ガスを吸収するだけでなく、地面に水分を保つダムのような役割も果たす。しかし、干ばつが起こると生活のためにまた木々を切り倒し、発電に使ったり農地を増やしたりするため、悪循環が起きている。

© Paul Balfe
2. マダガスカルの熱帯雨林(マダガスカル)
アフリカ大陸沖、インド洋に浮かぶ大きな島国、マダガスカル。海岸線は森に覆われ、中央部は標高1000~2000mの山々が連なる。水源豊かで、山の谷間には川が流れる。高低差の激しさのおかげで、古来、マダガスカルには多様な生物が暮らしている。
動植物の約8割は固有種で、樹木は約4000種が確認されている。世界にあるバオバブは全部で8種類だが、その6種類がマダガスカルの固有種でもある。ワオキツネザルやテンレックなど動物だけでなく、爬虫類や両生類、昆虫や鳥類の多様性は、世界でも類い稀なものだ。
しかし、現在は違法な森林伐採により、緑の森は失われ、土壌がむきだしになっている箇所も多い。香り木として利用される白檀(ビャクダン)紫壇(シタン)は高価なため標的になりやすい。また、生活のための燃料にも木々が使われつつある。
それに加え、古くからの伝統である焼畑農業のタヴィも裏目に出ている。土に栄養がなくなると森林を燃やし、また違う田畑に移るという農法を、マダガスカルの人口の7割を占める農民のほとんどが行っている。
1950年から2000年ごろまでに約半分の森林が消滅したとされている。

© Aleix Cabarrocas Garcia
3. チャド湖(チャド)
アフリカ大陸の中央部にあり、チャド、ナイジェリア、ニジェール、カメルーンの4カ国にまたがるチャド湖。砂漠のなかの貴重なオアシスであり、周辺国に水を供給し、また漁業も盛んに行われてきた。水や食料、休息を求めて家畜を連れて移動する遊牧民の姿や、湖畔の村で行われる定期市など、昔ながらのチャド湖の暮らしが息づいている。
しかし、かつては世界6番目の湖面面積を誇ったチャド湖は、1963年から2001年の間に95%も縮小。その原因は、もともと水深が低いことに加え、気候変動と急激な農業用水の需要の高まり、湖周辺の過放牧が挙げられる。2000万人の飲料水となっているチャド湖の枯渇は、今後「水戦争」を起こしかねない。圧政や汚職、病気の蔓延など、水不足は諸悪の原因となる可能性がある。チャド湖以外にも、アフリカ中央部ではさまざまな湖、川などが砂漠化しており、各地で同様の問題が起きている。

© EU Civil Protection and Humanitarian Aid
4. キリマンジャロの氷河(タンザニア)
アフリカ大陸最高峰、5895mの高さを誇るキリマンジャロ。赤道付近、熱帯地域にあるが、山頂には氷河が存在する。その美しい光景をいつかは見たいと、多くの登山家が憧れる名峰だ。
nbsp;
しかし、氷河は急速に融解しつつあり、1988年から2008年にかけて、氷河の面積は3分の1から半分にまで縮小。原因は一言で温暖化だとは言えないことがわかってきている。キリマンジャロは火山でもあり、その地熱が氷河の融解に関係しているという説もある。また、山麓での樹木伐採によって山の保水力が落ち、大気が乾燥することによって、氷河が昇華(解けずに蒸発)しているとも言われている。

© Christoph Strässler
5. グレイシャー国立公園の氷河(アメリカ)
アメリカ北部・モンタナ州にあり、カナダと国境を接しているグレイシャー国立公園。国立公園のなかでは比較的観光化されておらず、手付かずの自然が残っており、荒々しい山々と輝く青い湖、そして氷河がつくりあげる神秘的で雄大な景色が魅力だ。
グレイシャー国立公園は、数千年をかけて氷河により地形が削られ、尖った山脈や深い谷など起伏に富んだいまの地形になったとされていることから、「氷河がつくった美術館」と呼ばれている。
19世紀後半までグレイシャー国立公園にあった150箇所の氷河(25エーカー以上)は温暖化によって今では25個まで減少している。グレイシャー国立公園だけでなく、アメリカの国立公園内に存在する氷河は直近50年間で急激に縮小し、今後数十年内で溶けてなくなるという調査結果もある。

© Scutter
6. エバーグレーズ湿地
エバーグレーズはアメリカ・フロリダ半島の南部に位置する大湿地帯であり、一年中温暖で、亜熱帯の自然を楽しむことができる国立公園。水深30cmの浅瀬を草が覆っていることから「草の川」とも呼ばれている。
生命の源である水が豊富なエバーグレーズは動植物の宝庫で、フラミンゴやトキ、カワウソやシカ、ピューマ、アメリカワニなどの野生動物が生息しており、マングローブ林が広がっている。
しかし、近年、温暖化により発生回数が増えているハリケーンや海面上昇の影響を受け、海水による浸食や湿地の後退が深刻になっている。また、河川に流出した化学肥料や外来種が動植物を脅かし、レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)の登録数は増えている。

© Diana Robinson
7. アマゾンの熱帯雨林(ブラジル)
2019年夏、世界最大の熱帯雨林アマゾンをはじめとして大規模な火災が発生。その数は、1カ月で約3万件。2011年以降、アマゾンでは毎年8月に約2万件程度の火災が起きているが、これを大きく上回った。
自然発火による火災だけではなく、人為的な原因もある。たとえば、土地開拓のために製材業者が樹木を伐採したあと、投資家が残った植生に放火して更地にし、農家や牧畜業者に販売しようと目論んでいるなど、意図的なものも多い。ボルソナロ大統領がアマゾン川流域の開発拡大を主張していることで、こうした慣習がいっそう大胆になり、処罰を免れている人も多くいると予想される。
アマゾンの熱帯雨林は、大量のCO2を吸収し、また水蒸気を放出して南米大陸全体に雨を降らせている。アマゾンの火災を放っておくと、地球全体の気温が上昇する可能性があると専門家は指摘している。

© Neil Palmer/CIAT
8. ウユニ塩湖(ボリビア)
真っ白な湖面が、空も、人も反射して、まるで鏡の世界にいるようかの不思議さが味わえるウユニ塩湖。標高3700mという富士山と同じくらいの高さにあり、広さは岐阜県とほぼ同じの1万620㎢。アンデス山脈が海底から隆起した際に、大量の水が山上に残ってできたといわれている。高低差がほとんどなく平地であることから、水が流れ出ることがないのだ。
いつかは行ってみたいと思うこのスポットも、実は危機に晒されている。というのも、塩原の地下には世界のリチウム埋蔵量の17%が埋まっていると推定され、開発が進められているのだ。リチウムはパソコンやスマートフォンなど電子機器に欠かせない原料であり、今後も需要はつづくと考えられる。
また、ボリビア政府は自国の貧困を解消する手段として、塩原の開発に期待している。

© Michael Tieso
9. 死海(イスラエル・ヨルダン)
生物が存在できないほど高い塩分濃度(約30%)から、「死海」と呼ばれるヨルダン渓谷に位置する巨大な湖。ヨーロッパの人びとを中心に、世界中から観光客が訪れるリゾート地であり、死海に浮かんで家族とのんびり過ごすことや、またリウマチや皮膚炎などの療養や美容などを目的として多くの人が訪れる。
しかし、死海の水位は年々低下しており、このままでは2050年までに干上がってしまうといわれている。というのも、死海が唯一の水源となっているヨルダン川から近隣諸国が飲料水や工業用水、農業用水として大量に水を汲み上げているからだ。
イスラエルとヨルダン政府は200㎞離れた紅海から海水を汲み上げ、パイプラインをつないで死海に流し入れるという苦肉の策を計画中だ。

10. グレートバリアリーフ(オーストラリア)
オーストラリア北東部クイーンズランド沖で、2300㎞つづくサンゴ礁群であるグレートバリアリーフ。世界からダイビングやシュノーケリングに人びとが集まるのは、水の透明感はもとより、色鮮やかな海の生き物に出会えるから。1500種を超える魚に、200種もの鳥が生息している。
海洋生物の多様性が豊かなのは、400種を超えるサンゴのおかげだ。200万年前から堆積した石灰岩の上で生きつづける巨大なサンゴ礁は、生き物の棲み家となり、その繁殖を手助けしてきた。
近年、海水温の上昇や水質汚染でサンゴに大きなストレスがかかり、サンゴの白化現象が起きていて、長引けば死滅してしまう。サンゴ礁は全世界の海洋面積のたったの0.2%を占めているにすぎないが、海洋生物の4分の1から3分の1はサンゴ礁に棲んでいると言われるほど、生物多様性を生み出している。サンゴを失うことは、そのほかの多くの生物を失うことにもつながっているのだ。

© Paul Asman and Jill Lenoble