
アメリカ大陸で生まれたカカオ豆が、海を渡り、かたちを変えて、世界中でチョコレートが食べられるようになった今。ショコラティエたちは自分のチョコレートづくりを求めて、再び産地に還る。ビーントゥバーのつくり手たちに、旅の話を訊いた。
日本からは、東京・蔵前の喫茶室〈蕪木〉でチョコレートづくりをしている蕪木祐介さんに、カカオをめぐる旅の紀行文を寄せていただいた。
Photo & Text:Yusuke Kabuki
旅とチョコレート、そのはじまり
私はカカオと珈琲を生業としている。
今でこそアフリカは、仕事で何度も足を運んでいる大好きな土地だが、初めて西アフリカのガーナ行きの便に乗り込んだときの、アフリカの人びとに囲まれて圧倒された記憶、薄暗い空港に到着したときの不安感、ふわふわと漂う、病気を媒介する“蚊”に対する異常な緊張感、それらの感覚は今でも忘れられない。
旅は子どもの頃から好きだった。もともと知らない土地を探検するのが大好きな子どもであったが、初めての旅といえるものに出たのは、少年時代のこと。地元の福島から電車を乗り継いで鈍行電車で5、6時間かけて行った、岩手・遠野の旅だった。柳田國男の妖怪の世界に憧れて、だった気がする。それから、青春18きっぷを握って貧乏旅行に出ては、ヒッチハイク、野宿など、親にも散々心配をかけた。大人になってもとにかく出歩くのは好きだったが、まさか自分がアフリカの地に立つことになるとは思わなかったし、不思議な人生だなと感じる。

アフリカの長閑な景色。マダガスカル北部、アンバンジャにて。
〈蕪木〉のチョコレート。東京・蔵前の店舗兼工房で、マダガスカル、タンザニア、エクアドル、ハイチ、ベネズエラ、キューバ、ベトナムなど、世界各地のカカオ豆からチョコレートづくりをしている。お店ではホットチョコレートやチョコレートを使った季節のお菓子もいただける。
初めてのガーナ
初めて訪れたカカオの生産国が、ガーナであった。
福島で生まれ育った私は、子どもの頃から同郷の野口英世について教わってはいたが、そのときは名前こそ知っているものの、恥ずかしながらどんな偉人なのかも知らなかった。彼の研究した黄熱病のワクチンを打ち、そして彼が亡くなった首都アクラに立ったとき、勝手に感慨深くなったのを覚えている。
チョコレートといえばガーナと思われる方も少なくはないのではなかろうか。板チョコレートの名前にもなっているとおり、世界でも有数のカカオ生産国で、日本に輸入されているカカオ豆の大部分はガーナのものだ。とはいえ、そもそもカカオの原産国は中南米であり、中南米と比べるとガーナはカカオ生産において新興国ではある。大航海時代に中南米の作物であったカカオが西欧の文化と出会い、“チョコレート”というかたちに昇華されていくなか、カカオ豆の需要も高まり、西欧諸国は自国の植民地で新たにカカオ豆を栽培し、増産させていった。西アフリカでは収量が多く、かつ病気にも強い品種を植え進めて改良されていったため、今となってはコートジボワールに次いでガーナは世界第2位のカカオ生産国となっている。




左/初めて手に取ったカカオポッドを写真に収めていた。「アメロナード」という小型の品種。ガーナ・テテクワシ農園にて。
右/ガーナのカカオ栽培のルーツ、テテクワシ農園のカカオの樹。
生産国の子どもたちとのチョコレートづくり
12年ほど前のガーナ訪問の目的は、農園視察やさまざまなものがあったが、その一つがガーナで育つ子どもたちへのチョコレートワークショップだった。アフリカのカカオ農園の子どもたちはチョコレートの味を知らない。これを聞くと貧しさや、児童労働のような暗いイメージが湧くかもしれないが、そもそも熱帯のガーナではチョコレートは溶けてしまって流通できないからというのが大きいし、クーラーもない熱帯の暑さのなか、チョコレートを食べたいとはあまり思わない。
そのかわり、彼らがよくカカオの果肉を頬張るシーンによく出くわす。そのライチのような瑞々しい果実の美味しさは、チョコレート消費国の人びとは知らない。そのようなこともあって、私自身、彼らがチョコレートを食べないことを可哀想とは思わないが、彼らが育てたカカオがどのようなものに変化するのか、そしてそれがどれほど美味しいものなのかを共有することで、彼らとその家族たちが、少しでも家業に誇りや愛着をもってもらえればうれしいと思い、現地の小学生の子どもたちと一緒にカカオ豆からチョコレートをつくるワークショップを企画したのだ。

カカオの厚い殻を割ると、中から瑞々しい果肉が現れる。ライチやスウィーティを思わせる、甘く爽やかな味わい。メキシコなど北中米のカカオ発祥の国々では、現地の人もカカオドリンクを飲むことも多いが、アフリカではカカオ豆は圧倒的に換金作物の印象が強い。
ガスコンロとガスボンベは日本から持っていったが、すり鉢などの道具は現地で調達し、原料であるカカオ豆などは土地のものを用意していただいた。田舎の小学校に訪問し、そこでつくり上げたチョコレートはポロポロとしたお粗末なものではあったが、教室で手網を使ってカカオ豆を焙煎し、砂糖やミルクと擦り混ぜ、出来上がったものを口にしたときの子どもたち(そしてそこにいた先生たちも!)の興奮した様子は忘れられない。彼らはその日の夜は家でその出来事を家族に話しただろうか。農家である彼らの家族の皆が、誇らしげにカカオのことを話し合っているような笑顔の時間を過ごせていたことを願う。
誇らしく仕事をすること
美味しいカカオを求めてアフリカやアジアを旅していて感じるのが、美味しいカカオをつくることに力を注ぐ農家さんはほとんどいないということ。その理由は、やはり彼らがチョコレートの味を知らないことが大きいだろう。たとえば、ワインのようなつくり手、売り手、飲み手の距離が近い嗜好品と異なり、チョコレートは生産国と消費国の、物理的そして心理的距離が遠い。カカオ豆に対する情熱や想いや価値の共有は、課題の一つだ。
ではどうやったら美味しいカカオをつくってもらえるかというと、私は金銭と誇りだと感じている。良いカカオに対して正しく評価し、見合った対価があること。生産者に敬意を払い、互いに誇らしく仕事をできること。アフリカで暮らし、生活する彼らの感覚を理解するには、あまりに共にする時間が短すぎるが、今こうして彼らの手がけたカカオを使ってチョコレートをつくり、皆さんに食べてもらう仕事をしているなかで、お客様に美味しいものをお届けして、豊かさを提案すると同時に、自分たちの上流にあるカカオ生産者さんたちも、幸せで恙無い暮らしをしてもらいたいと願っている。そのために、小さくてもいいから私たちができることを行動に移すことは意味のあることだと信じている。当時、カカオのワークショップに参加してくれた子どもたちは、今はもう成人している。何人かはカカオの仕事をしているのだろうか。今でもあのときの経験から、自身で収穫したカカオを調理している子もいるだろうか。

ガーナでのカカオ生産風景。発酵させたカカオ豆を天日乾燥している。
カカオのテロワールのこと
カカオ農園の話をしているが、日本ではカカオの樹などはほとんど見る機会もなく、甘美なチョコレートが、農作物からできるというイメージはしにくいかもしれない。大雑把に説明をすると、熱帯の植物であるカカオはラグビー状の果実を幹にたわわに実らせる。その果肉を収穫し、発酵させ、残った種の部分を乾燥させたものが、チョコレートの原料であるカカオ豆だ。そのカカオ豆を焙煎して香りを引き出し、砂糖や乳などの原料と混合し、粒子をきめ細かく整え、最後に長時間練り上げて香りを整えてできるのがチョコレートだ。

ベトナムの中部高原のカカオ畑。手入れが行き届いていて美しい。
カカオ豆も農作物である以上、ワインやコーヒーと同様、栽培される品種、土壌や気候などによる風味特性をもっている。ガーナをはじめとした西アフリカのカカオは、チョコレートらしい苦味とコクが特徴で、しっかりとした苦味はミルクのコクにも負けず、ミルクチョコレートにも仕立てるととてもバランスが良くなる。同じアフリカでも島国であるマダガスカル産のカカオはベリー系のフルーティな香味が素晴らしい。タブレットに仕上げると、まるでフランボワーズを練り込んでいるのではないかという果実感をもつ。カカオのルーツである中米の原種に近いカカオは、ガーナ産のものと対照的で苦味が少なく、クリーミーで、香りや酸味が強い。その中でも複雑な香りをもつベネズエラ豆、フローラルな印象のエクアドル豆などは、ブランド豆として世界中で重宝されている。

カカオ豆は色だけではなく、丸かったり尖っていたりゴツゴツしていたりと、系統によって見た目も異なる。
余談ではあるが、私がカカオの仕事に興味をもったのも、カカオのテロワール(生育地の地理、地勢、気候による風味特徴)の豊かさに驚きを感じたところからだった。喫茶店の街(と私が思っている)、岩手の盛岡で過ごしていた若い時分、珈琲と喫茶文化に強い興味をもち、珈琲店で勤めたり、書籍を漁ったりしながら、珈琲の学びを深めていた時代があった。当時はスペシャルティコーヒーという言葉が生まれ始めた時期。深めれば深めるほど、さまざまな新しい香味の珈琲と出会いがあり、驚きと喜び、発見のある毎日だった。そんななか、たまたま図書館で手に取った本にカカオの生産国の話とその製法、テロワールの話が載っており、スペシャルティコーヒーにも似たチョコレートの上流のカカオの世界の広がりに驚き、興味が湧き、あれよあれよとチョコレートの世界に足を突っ込むこととなったのだった。

マダガスカルでの生産風景。収穫したカカオの実を割り、中の果肉を取り出しているところ。
ベトナムで“よいカカオ”をつくる
テロワールといえば、アジアでもインドネシアやマレーシアを中心にたくさんのカカオ豆が栽培されている。しかし、中米やアフリカのブランド豆と比べて、注目されているとは言い難い。そのなかでも私は10年近く、ベトナムの中部高原のカカオ農園に足繁く通っている。たとえばカカオを求めてアフリカのさらにはその地方部へ行くと、とても物珍しい目で見られ、声をかけられ、一気に注目されるので落ち着いて歩けたものではないのだけれど、このアジアの片田舎では、国民性もあるのかもしれないが、皆同じ黄色人種、こちらを強く気にすることはなく、程よい気持ちで過ごすことができる。さらには、少数民族のお母さんに家の食事に誘ってもらったり、村の若者たちの宴会に混ぜてもらえたりと、土地の人びとが食べるものと同じものを飲み食いし、同じように朝の市場で買い物をして、その暮らしを感じることができる。カカオ旅の醍醐味の一つだ。
ベトナムに足を運ぶようになったのは、そこに住んでいた日本人の方から、まわりにカカオの木がたくさんあり、貧しいこの土地の地域活性化のために美味しいカカオをつくりたい、と相談を受けたことがきっかけだった。ちょうど前職のカカオ・チョコレートの開発の仕事に区切りをつけた時期で、時間だけはあったので、人情厚いその方の人柄にも惚れ、たびたび訪問するようになった。ふだん生産国ではモチベーションとして聞くことのない、“美味しいカカオをつくる”という言葉に惹かれてしまったのかもしれない。




上/ベトナムでお世話になっているカカオ農家のタムさん。ここのカカオから生まれる香ばしい味わいは、綺麗な農園管理と丁寧な栽培から。カカオの風味にも性格が現れる。
下/タムさんが、カカオを運ぶために若い時分に借金を叩いて買った、日本製の原付バイク。今でも現役でカカオを運んでいる。
発酵の沼をいく
ここ最近、私が取り組んでいるのが、カカオの発酵を深めること。
案外知られていないが、チョコレートは、風味をつくるうえで“発酵”という工程が極めて重要な食品である。発酵次第で、香りの深みが変わってくるのだ。訪問していたベトナムの中部高原の土地でつくられるカカオの香味は十分美味しいものではあったのだが、もう一歩深みが欲しいと考え、注目したのが「発酵」の行程。それまではある程度効率よく、それなりの品質になる発酵を現地の農家では行っていたが、もう少し特徴のある香味をつくりあげるために、また雑味を減らすために、発酵による品質向上の余地があると考えた。

マダガスカルのカカオの発酵風景。
ところが、いざトライしてみると、卓上の理論だけでは太刀打ちできず、トライアンドエラーの繰り返し。一筋縄ではいかず、完全に泥沼にハマってしまっている。失敗だらけで、もはや改良試験というよりは自分の勉強に近い。いまだに着地点がぼやけたままではあるが、苦労を通して、その発酵の重要性を身をもって感じている。
発酵に使う木箱や上から被せるバナナの葉などに付着している自然の酵母菌がカカオの発酵を進めてくれるため、私がやることといえば、収穫してもらったカカオの殻を割り、果肉を取り出し、木箱に入れること、そして温度や様子を観察しながら、良きタイミングでカカオの攪拌をさせていく。撹拌して空気を取り込ませることで、活動する微生物の種類が変わるので、このタイミングもまた難しい。甘酸っぱくて瑞々しいカカオの果肉は、徐々にワインのような発酵香をまといながら流れ落ち、さらに発酵が進むとお酢に変化していき、ツンとした香りがカカオ豆に残る。この決して心地よい香りとはいえない刺激臭が、カカオ農園らしさを一番感じさせてくれる香りだ。試験については、いまだに着地点がぼやけたままではあるが、発酵の大切さと可能性を、身をもって感じている。

ベトナム中部高原のカカオ豆。畑に通っていると、改めて、その色形、実のなり方など、不思議な植物だなと思う。
それにしてもカカオ豆の生産はとても大変な作業だなと、毎度感じる。
カカオの実は、赤、緑、黄色、紫など色がさまざま。また、品種によって熟す際に色も変化するため、収穫は経験も要するうえに、すべて手作業。割ってみると未熟、なんてことがあると、糖度が低くて発酵には使えない。さらに収穫した何百kgのカカオの実を発酵場に運ぶだけでも途方に暮れてしまう。さらには、1〜2cmくらいの分厚い殻を一つひとつ鉈で割って中身の果肉を取り出す作業を延々と続けるのは、いつも心が折れそうになる。1週間の発酵、そしてその後の1週間以上の天日乾燥。カカオ豆をつくるだけでも相当な手間暇がかかる。最近でこそ異常気象でのカカオの不作によってチョコレートの値段が上がっているが、それでもカカオ生産者が流す汗の量に対して、スーパーで売られている板チョコレート1枚の値段は安すぎるなと感じてしまう。

木箱に入れたカカオの果肉は、数日後には酵母菌の力で糖分がアルコールに変わる。果汁は微発泡し、果実酒のような甘く爽やかな香りに包まれる。
チョコレートの奥にある風景
チョコレートをつくることは、自分なりの“美味しさ”を追求することに他ならない。それと同時に、生産現場の苦労、暑さ、強烈な香り、強い日差し、疲れ、流す汗、雨と泥、土、自分が見た景色、肌に触れた空気を少しでも身をもって感じることで、味に反映されるものもあると信じている。
苦労だけではない、これまでカカオの旅をとおして、たくさんの優しさに出会ってきた。ガーナの田舎町の族長の屈託のない笑顔、マダガスカルで航空券をなくしたときに、ネットカフェのような場所で必死に助けてくれた若者の優しさ。エチオピアにて腹痛で寝込んだときに、土地のハーブを使ったお腹に優しい珈琲を振る舞ってくれた青年の真心。ジャワで道案内をしてくれ、別れ際に涙を流してくれたガタイの良いあんちゃん。ベトナムのバンメトートの安宿で長く滞在中に高熱にうなされたときは、宿のおばあちゃんが丁寧に看病してくれた。
人の優しさに触れて、心遣いや思いやりの気持ちを共有することで、さらにカカオの国の魅力を深めてくれている。きっとそれらの経験と記憶、感情が、自然とチョコレートの味に詰まっていくだろう。旅のエッセイを読むように、一片のチョコレートをゆっくり味わっていただきたいと思う。もしかしたら、その奥にいろんな景色が見えてくるかもしれない。

東京・蔵前にある〈蕪木〉の喫茶室。
Profile
蕪木祐介(かぶき・ゆうすけ)
福島生まれ。大学時代を過ごした岩手で喫茶文化に出合い、大学の研究でチョコレートにも興味をもつ。製菓会社でチョコレートづくりに携わった後、2016年より東京でコーヒーとチョコレートの喫茶室〈蕪木〉をはじめる。2018年、岩手・盛岡でコーヒーとチョコレートをいただける〈羅針盤〉も開店。著書には『チョコレートの手引』『珈琲の表現』(雷鳥社)、コーヒーの原木を探しにいく旅を記した冊子『珈琲の旅 Ethiopia』の制作も。
福島生まれ。大学時代を過ごした岩手で喫茶文化に出合い、大学の研究でチョコレートにも興味をもつ。製菓会社でチョコレートづくりに携わった後、2016年より東京でコーヒーとチョコレートの喫茶室〈蕪木〉をはじめる。2018年、岩手・盛岡でコーヒーとチョコレートをいただける〈羅針盤〉も開店。著書には『チョコレートの手引』『珈琲の表現』(雷鳥社)、コーヒーの原木を探しにいく旅を記した冊子『珈琲の旅 Ethiopia』の制作も。
Information
蕪木
東京・蔵前にある自家焙煎のコーヒーとチョコレートの店。工房が併設された店内の1階ではチョコレートやコーヒー豆を購入できて、2階の喫茶室ではコーヒー、チョコレート、酒類、チョコレートを使った季節のお菓子が愉しめる。
住所
-
Instagram
-
HP






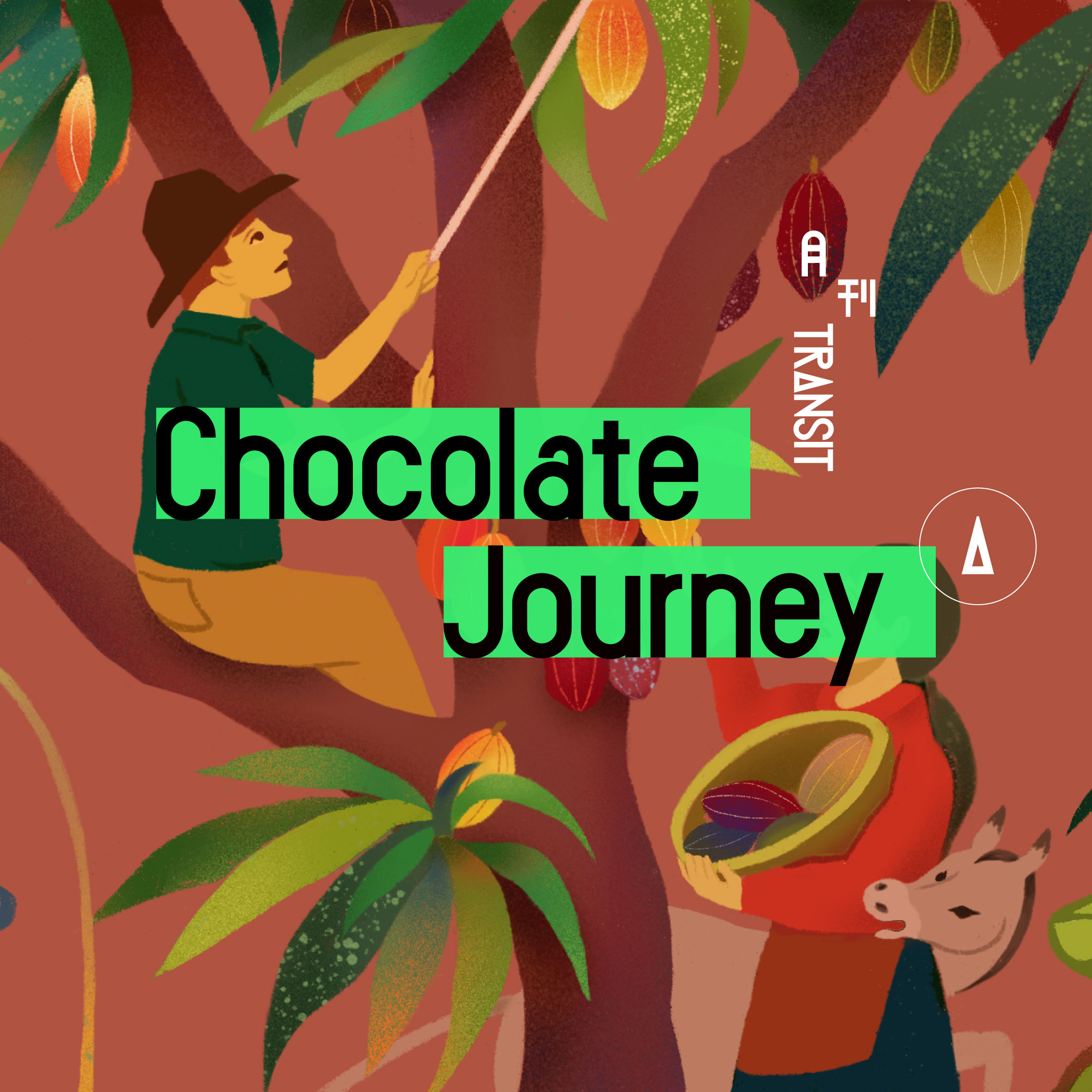








-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























