
3月18日は精霊の日(しょうりょうのひ)。
歌人として名を馳せた柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)、和泉式部(いずみしきぶ)、小野小町(おののこまち)の3人の忌日がいずれも3月18日であると伝えられていることにちなんで制定されました。

年老いた小野小町。(『卒塔婆の月』月岡芳年『月百姿』より)
精霊(しょうりょう)とは、日本において古代から受け継がれてきた概念の一つ。
もともとは、祖先や亡くなった人びとの霊が特定の時期にこの世に戻ってくると信じられたことに由来し、日本では、夏の精霊流しやお盆など、亡くなった人びとの魂を慰める風習が現代までつづいています。

おわら風の盆(富山市)。
© akiko yanagawa
精霊信仰は、仏教や神道の影響を受けながらも、日本独自の思想として発展してきました。
その起源は、古代日本のアニミズム的な世界観に遡ります。古代の人びとは、山や川、樹木や岩など、あらゆる自然物に魂が宿ると考え、それらを敬いながら生活していました。
この考えは、神道の「八百万(やおよろず)の神」という概念にもつながり、日本の信仰文化の基盤となっていきます。また、祖先の魂が特定の時期に現世に戻ってくるという考え方も生まれ、それが後のお盆や精霊流しなどの風習に影響を与えました。

深山で修行をする山伏。
© 唐山健志郎 (Kenshiro Karayama)
時代が進むにつれ、精霊信仰は仏教とも結びついていきます。
仏教が伝来すると、日本人は死者の魂の行方についてより深く考えるようになりました。特に浄土信仰が広まると、人びとは死後の世界や祖先の供養を重要視するようになります。こうした背景のなか、日本では祖先の魂を迎え、再び送り出すという独自の習慣が形成されたといわれており、全国各地で行われている精霊流しや灯籠流しは、古代からの信仰の一環として今に受け継がれています。

精霊流しに使用する精霊船には、個人で流すものと、自治会などの地縁組織が合同で出す『もやい船』の2種類がある。戦前はもやい船が主流で、個人で船を造るのは富裕層に限られていたそう。写真はもやい船の印灯篭。
© Sonic883
現代においても、精霊信仰はかたちを変えながら生きつづけています。科学が発展し、合理的な考え方が普及した現代でも、自然や祖先を敬う心は失われていません。お盆の時期には多くの家庭で先祖供養が行われ、地域によっては伝統的な精霊祭りもつづいています。
春の訪れとともに、桜が咲きはじめる頃合いです。花を愛でながら和歌を詠み、先人たちが託した言葉に耳を傾けるひとときは、日本の文学や文化の奥深さを感じる、風情ある過ごし方かもしれません。
Keywords
SEE ALSO関連記事
TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto
NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!
COUNTRIES
View All
CATEGORIES
View All

Kasane Nogawa
ABOUT US
TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、
地球上に散らばる
美しいモノ・コト・ヒトに出合える
トラベルカルチャーメディアです
MAGAZINES&BOOKS
Back Numbers



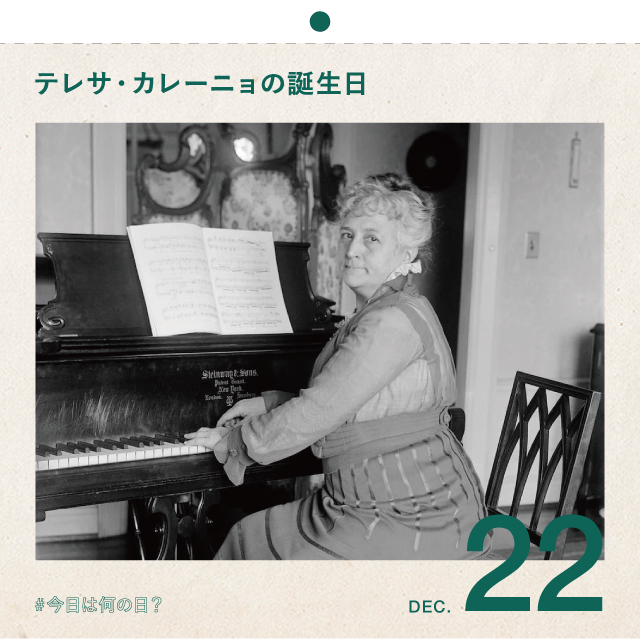





-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)




















