
月刊TRANSIT/瀬戸内一周!
TRAVEL&EAT
2025.04.15
15 min read
住んでよし、旅してよし……そんな広島、愛媛、香川、岡山の瀬戸内4県をローカル視点でまわろうと、その土地の友人の声を頼りにぐるり一周ドライブへ出かけた。
広島のキーワードは、“島と農”。
一緒に旅をしたのは、広島・因島出身で農業と写真を仕事にしている上原和人さん(この企画の撮影も担当!)。そして広島生まれのマツダの「MX-30 ROTARY-EV」。
柑橘畑、産直カフェ、町の食堂から夜の尾道まで。1泊2日でしまなみ海道、とびしま海道を駆け抜けた!
Photo : Kazuto Uehara
Text:Maki Tsuga(TRANSIT) Cooperation:MAZDA
Index
15 min read
いざ、柑橘の島へ!
友人と「次に旅するならどこにいく?」と同じくらいよく話すのが、「住むならどこがいい?」という話題。
そんなとき私が真っ先に思い浮かべる風景のひとつが瀬戸内だ。実際にそこに暮らしている人たちは、どんなふうに瀬戸内を見ているんだろう、どんなふうに地元を旅するんだろう。それが地元の知人たちの声を頼りに瀬戸内を一周ドライブしようという旅のはじまりだった。
そんな瀬戸内一周旅に誘ったのが、因島(いんのしま)に暮らすフォトグラファー上原和人さんだった。瀬戸内の島で農業と写真をやっているおもしろい子がいるよと知人の写真家から教えてもらって、以前、しまなみ海道を和人さんに案内してもらったことがあったのだ。
そしてもうひとつの旅の仲間が、広島生まれのマツダ。ロングドライブに頼れる車をということで、「MAZDA MX-30 ROTARY-EV」で旅をすることに。 広島で旅の仲間たちと合流して、瀬戸内一周のはじまり、はじまり!

1920年の創立から広島に拠点を置くマツダ。本社の中には、マツダの歴史がわかるマツダミュージアムもある。




上/プラグインハイブリッドの「MAZDA MX-30 ROTARY-EV」。100km超のEV走行ができて、バッテリーが減ってくるとマツダ独自技術のロータリーエンジンで発電を行う。充電の不安を気にせずに、環境にもお財布にもやさしく走れる。 下/家から海まで走って10秒という環境で育った上原和人さん。高校時代はパイロットを目指していたことも。

まず目指したのは、和人さんが暮らす因島。
レモン、温州みかん、ネーブルオレンジなどなど、日当たりがよくて水はけのよい斜面を好む柑橘は、瀬戸内の島々と相性ぴったりだ。広島や愛媛には数々の柑橘が栽培されていて、島によって少しずつ得意な品種が違ったりする。
因島は八朔発祥の地。安政柑(あんせいかん)という在来の柑橘もある。因島で柑橘の種類が豊富な理由は諸説あるけど、そのひとつが村上水軍説なのだと〈comorebi farm〉の小嶋正太郎さんが教えてくれた。




柑橘農家comorebi farmを起ち上げた、東京・新宿出身の小嶋正太郎さんと広島・福山出身の名部絵美さん。comorebi farmが八朔のナチュラルクラフトサイダー「ISLANDER」は県外のセレクトショップで目にする機会も。
「因島は村上水軍が拠点を置いていた島のひとつで、彼らは瀬戸内の水運を取り仕切るだけじゃなくてアジア諸国や日本各地と交易していたから、いろんな柑橘の品種が因島に持ち込まれたんじゃないかといわれてるんです」と正太郎さん。
村上水軍が活躍していたのは中世のこと。21世紀から一気に数百年前へ、目の前の瀬戸内海からアジアの外洋までつながって、ちょっとロマンのある話。
因島をはじめ瀬戸内には柑橘栽培をしている島々がたくさんある一方で、耕作放棄地も増えてきている。斜面につくられた柑橘畑は農作業もひと苦労。農家さんが高齢になると畑を維持するのが難しい。正太郎さんと絵美さんは、そんな放棄された畑を受け継いで柑橘を育てている。
「耕作放棄地に生えやすい竹や姥目樫(うばめがし)は、根が浅くて土砂崩れの心配があるんですよね。島の風景を守るためにも柑橘畑をつづけたほうがいいんですよ」と絵美さんが教えてくれた。

山の上にある資料館・因島水軍城本丸には、因島村上氏が残した遺品や古文書を展示されている。村上水軍は14世紀頃から瀬戸内海で活動していた水軍。造船、操船、海の戦闘に長けていて、とくに広島の因島、愛媛の来島(くるしま)、能島(のしま)を拠点に、瀬戸内の水先案内、輸送、略奪、戦闘を行っていた。1588年、豊臣秀吉が公布した海賊禁止令で表舞台から姿を消していく。
comorebi farmには、旅人、子連れの家族、料理人、大学生、移住先を探している人など、いろんな人たちがやってくる。農業体験ができるファームツアーをやっていて畑を訪れやすいというのもあるし、正太郎さんは編集、絵美さんは企業のPRやしまなみ映画祭を企画する仕事もしながら兼業農家をしていることもあって、いろんな仕事の縁があることもその理由。柑橘畑が、島外の人たちが因島を訪れるきっかけにもなっているのだ。

comorebi farmで育てている柑橘3種。左から八朔、レモン、安政柑。安政柑の味わいは八朔に似ていて、酸味、甘み、ほろ苦さのバランスが絶妙。さっくりドライな食感もいい。
和人さんもcomorebi farmの畑に通いながら挑戦していることがある。
「瀬戸内で栽培された柑橘は、そのまま果実を販売することもあるけど、多くは消費期限の長いジュース、ジャム、スイーツに加工されるんですよね。そのときに大量に皮が廃棄されるので、それを使ってなにかできないかなと思って、今、精油づくりをしているところなんです」
精油の名前は〈nagomu OiL〉。試作品でもらった八朔の精油は、まさに皮を剥いたときのような生き生きとした目の覚めるような香り。レモン、八朔、安政柑など、いろんな品種で試作中とのこと。柑橘ごとの香りの違いも気になる。


因島の新旧農業イノベーション!
comorebi farmの畑を後にして、海沿いの〈COGO〉へ向かう。使われなくなっていた保育園を改装した産直カフェで、和人さんの高校の同級生で農家をやっている加藤靖崇さんとパートナーの志穂さんがはじめたスペースだ。

園庭だったところには、軽トラが数台並んでいる。靴を脱いで中に入ると、地元のおじいちゃんたちがお茶を飲みにきているところだった。
COGOでつくったハーブティーや柑橘のケーキを注文。ケーキは志穂さんの手作りなので、何があるかはそのときのお楽しみ。この日いただいたのは安政柑のチーズケーキ。柑橘とチーズの爽やかな酸味と甘みが合う! 店棚には他の農家さんが栽培した農作物も販売している。
「自分でつくった野菜やハーブティーは通販や出張販売で売っているんですが、できれば島内に農家と消費者が直接やりとりできる場所がほしかったんですよね。それでこのCOGOで農作物を販売したり、カフェでその場で口にしてもらえるようにしたんです」と靖崇さん。
お店を切り盛りする加藤靖崇さんと志穂さん。靖崇さんは「みなと組」という名義で因島の農業を発信中。窓際にいたおじいさんは、シュロでハエたたきを制作中。絶妙なしなり具合が仕留めるのにちょうどいいそう。
ちなみにCOGOには、農機具メーカーのクボタの展示もある。実はクボタの創業者・久保田(大出)権四郎さんは因島生まれ。幼い頃に瀬戸内を行き交う船を見て自分も船を造れるようになりたいと思い、14歳で単身大阪に乗り込む。住み込みで働きながら鋳造を学び、自ら町工場を起ち上げて、水道管、農機具、船舶の部品も造るようになって、いまや世界トップ10に入る農機具メーカーになったのだ。
ふじ組の教室にあるクボタの展示。高低差のある因島は、昔は島内の移動も難儀していたところ、久保田権四郎さんが、道路、橋、公共施設を整備したという。COGOのすぐ近くにも久保田橋がある。
船に憧れた久保田権四郎に限らず、瀬戸内の人にとって船は身近な存在だ。
本州や別の島へ行くときに日常的に渡船を利用するし、船は働く場でもある。因島だけでなく、呉、尾道、今治といった瀬戸内沿岸は昔から造船業が盛ん。このあたりは外洋の沿岸よりも潮の干満の差が大きく、それが造船や船の整備に適しているんだそう。ちなみにマツダの前身となる東洋工業の創業者・松田重次郎も呉で造船の仕事をしていた経験がある。瀬戸内のイノベーション、恐るべしだ。




COGOの近くにある〈ミドリノコヤ〉にも立ち寄る。和人さんの姉・上原碧さんがやっているカフェだ。空き家を買い取って、知りあいの大工と一緒になって改修した場所で、目の前が穏やかな入江になっていて落ち着く。手作りナッツタルトのバーがとってもおいしい。サイクリストのエネルギーチャージにもぴったり。
行き交う人の街、尾道の夜
しまなみ海道を通って尾道へ渡る。
尾道は、広島と愛媛を結ぶしまなみ海道の起点で、国内外の旅人、サイクリスト、この周辺に暮らす人たちも集まる、このあたりの一大カルチャー都市だ。といっても、この賑わいは今にはじまったことじゃない。歴史を遡れば、平安時代から都に年貢を運び出す集積地として開港され、江戸時代には北前船が立ち寄るようになり、山の手には千光寺をはじめとする無数のお寺が建てられて、参拝客も押し寄せた。
尾道は、今も昔も変わらず、人も物も行き交う街だ。

夜の新開エリア。日曜日は空いていないお店も多くて静か。賑やかな雰囲気が見たければ金曜、土曜に歩くといい。
COGOの靖崇さんにもらったご飯処リストから、「地元の海鮮を食べるならここ!」というメモを元に向かったのが〈遊膳〉。尾道のアーケードをくぐり、新開(しんがい)地区へ。新開はもともと遊郭があった歓楽街で、現在はスナック、バーといったお酒を楽しむ場所から、寿司、焼き鳥、お好み焼きなどおいしい料理がいただけるお店が肩を寄せ合って並んでいる。
路地の先に〈遊膳〉の看板を発見! 高級クラブのような佇まいなうえに、窓がなくて店内が見えなくてちょっと入りにくいけれど……扉を開けると、カウンターにお客さんがずらり。カウンターの向こうでマスターと女将さんが出迎えてくれた。先客のみなさんが注文している料理がどれもおいしそう!みなさん常連のようで、「刺盛りは頼んだほうがいい」「巻物も絶対頼んじゃうな」「魚のこもね」「いかせんべいもいいよ」とお店の方と一緒になって自分のイチオシメニューを教えてくれる。
どれもおいしい&良心的なお値段! ちなみに「魚のこ」というのは魚卵のこと。お腹がいっぱいになった頃、おもむろにカウンターテーブルに出てきたのがデンモク……! 遊膳の第二部、カラオケが幕を開けた。
刺し身盛りをお願いすると、瀬戸内で獲れたタチウオ、コチ、デベラといった地魚が並んだ。「刺盛りに赤身のお魚がなくて驚いたんじゃない? 瀬戸内は白身の魚がおいしいんですよ」と女将さんがにっこり。タチウオは脂があって、コチは淡白ながら噛むほどに旨味を感じて、デベラはヒラメのエンガワのようなこりっとした歯ごたえで、どれもおいしい!

尾道を走る銀山街道。その昔、島根の石見(いわみ)銀山で採れた銀が尾道まで陸路で運ばれ、船で大阪まで運搬されていた。この街が栄えていた理由のひとつでもある。
とびしま海道の、農床と町の食堂
翌日はとびしま海道へ。
広島の呉市から安芸灘諸島を通って、愛媛県今治市の岡村島を7つの橋で結ぶルートだ。広島市街地から1時間ほど車で走ると、信じられないくらいのんびりした光景が広がる。
尾道と今治を結ぶしまなみ海道の橋とも違って、とびしま海道は一つひとつの橋が小さいので、その名前のとおり飛石を跳ねていくような感覚でドライブできる。海と道が近くて、そのまま海に吸い込まれてしまいそうな気持ちよさだ。




すれ違う車も少なく、のびのびドライブできる。とびしま海道は映画『ドライブ・マイ・カー』のロケ地にもなっている。
お昼ごはんにと立ち寄ったのが、大崎下島にある〈まめな食堂〉。人口300人ほどの久比(くび)集落にあって、元病院を改修した食堂だ。メニューは肉か魚の定食の2種類。この集落の住人たちに毎日食べに来てもらっても栄養バランスのがいいようにと、日替わりの献立を考えているそう。

木造の建物がかわいらしい、まめな食堂。右がこの食堂を起ち上げた更科安春さん。左が運営スタッフの一人、福島大悟さん。営業は11:30〜13:30の時間帯で木曜休み。
この場所を起ち上げたのは更科安春さん。東京生まれでアパレルの仕事をしてきたけれど、母親を自宅の介護で看取ったことをきっかけに、介護のない世界をつくれないか考えるようになったそう。そんなときに、偶然仕事で訪れた久比の住人たちが元気に農作業をしている姿を見て、ここにヒントがあると思った。
「80代の人たちが柑橘畑の農作業をしていたり、農床(のうとこ)といって家の前の家庭菜園を世話をしていたり、元気に生活しているのを見て、自然豊かな場所で自分の体を動かす暮らしって、なんて健康的なんだと思ったんです。ピン・シャン・コロリ(体がピンピンしているだけでなく頭もシャンとしている)でいけたらいいなと。久比の人たちに元気をもらうのと同時に、この集落の人たちにも元気でいてほしいという思いから、食堂をはじめました。元気なように見えても自分で料理するのが大変という高齢の方もいるので、出来合いのものじゃなくて、肉、魚、野菜を使った出来立てのごはんを食べて健康でいてほしい。食堂以外にも、訪問介護ができる看護師を呼んだり、できるだけ島を離れず暮らせる仕組みづくりもしていたりするんです」と更科さんは話す。


久比集落の農床を見せてもらう。ネギ、ブロッコリー、白菜が植わっていて、これから夏野菜を準備するところだそう。自分たちで食べたり、街で働いている孫たちに送ったり、近所の人とあげたり、まめな食堂に差し入れしている。
農床は久比ならではの文化で、同じ島でも他の集落にはこうした家庭菜園がないそう。久比の人たちは少しずつ違う種類の野菜を育てたり時期をずらしたりして、近所の人同士で野菜を渡し合う習慣があって、まめな食堂でも地域の人が農床でつくった野菜をお裾分けしてもらって、料理に使うことがあるのだそう。
「農」を通していろんな姿を見せてくれた広島。
名残惜しいけれど、とびしま海道の東端、岡村島からカーフェリーに乗って愛媛の今治に渡る。車と一緒に1時間20分ほどの船旅。愛媛はどんな出会いが待っているか……!




岡村港からは、車が乗れるカーフェリーと、人や自転車専用の旅客船があったり、「せきぜん渡船」が運行する今治行きの路線と、「大三島ブルーライン」が運行する大三島行きの路線があるので、行き先、乗船条件、時刻表をしっかりチェックしたい。乗船は先着順で、とくにカーフェリーを利用する場合は余裕をもって港に着いていたい。迷ったら岡村港務所に電話を(0897-88-2252)。しまなみ海道の下をくぐって今治港へ向かう!




Information
MAZDA MX-30 ROTARY-EV
マツダが世界で初めて量産に成功したロータリーエンジンを発電機として搭載。普通充電、急速充電に対応したプラグインハイブリッド自動車。100km超のEV走行ができて、さらなるロングドライブもロータリーエンジンによる発電で充電の不安なく運転できる。環境・走り・電動車としての利便性をうまくバランスさせ、気軽に、身軽に、環境に配慮した使い方が楽しめる。
-
MX-30 HP
-
MAZDA HP




















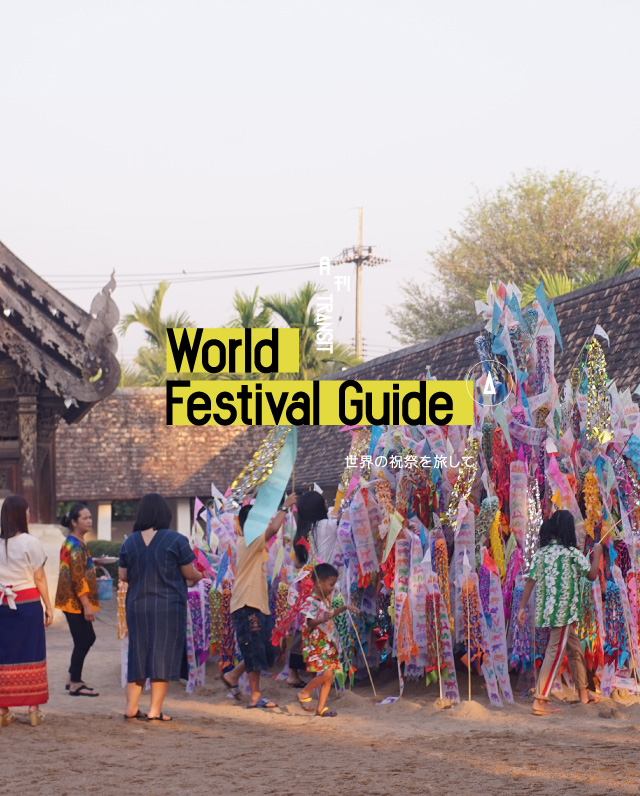





-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























