
カタネさんの夏休み
代々木上原の住宅街に2002年から店を構える〈カタネベーカリー〉。
1Fがベーカリー、地下はカフェ、隣は〈アコテ〉という生活用品店兼ワインショップ。3人も客が入ればもういっぱいになる極小のパン売り場に100種類以上並ぶパンは、どれもごくシンプルで定番の形。地域の人たちに愛される日常のパンだ。生地はもちろんフィリングもすべて手づくり。食材の多くも、生産者と顔の見える関係でつながり、納得したものだけを使っている。
カタネベーカリーを営むのが、店主の片根大輔さん。10代はパンクバンドのギタリストとして活躍し、のちにパンへと転向。ベーカリーチェーン〈ドンク〉で6年間修業、店長を務めたあと、28歳のとき妻の智子さんとカタネベーカリーを開店した。
そんな片根さんたちが大事にしているのが、旅すること。夏休みは6週間、よく働き、よく休むスタイル。カタネベーカリーによくいくお客さんたちからすると、「あぁ、今年もカタネさんの夏休みがやってきたんだな」と夏季休業明けを待ち遠しく思うかもしれない。でも、もしかしたらその夏休みにも、カタネベーカリーのおいしさの秘密があるのかも。
片根さんたちは夏の間、いったいどこへ行っているのか? 聞けば、国内外を旅していて、海外の旅ではパンの国フランスでアパルトマンを借りてゆっくり家族で過ごし、日本の旅ではお店で働くスタッフたちと一緒に生産者をめぐるのだという。
気になるカタネさんの夏休み、国内の北海道への旅に一緒に行くことにした。
中川農場

十勝のオーガニック小麦の草分け的存在。
ほぼ不可能だと思われていた大規模な農場での小麦生産に、道を開いた。
雑草取りに明け暮れて絶望の淵にあったとき、雑草を含めた動植物・微生物と共生していくビジョンを得たという。中川泰一さんの作る「愛の小麦」は、古代小麦も現代小麦も含めさまざまな小麦の種を混ぜて蒔く、多様性の小麦。特徴のある品種が助け合うのか、穂発芽(収穫前に雨にあたると小麦が穂についたまま発芽し溶けてしまう)などにも強いという。
カタネベーカリーと中川農場はもう10年以上も小麦を使いつづけ、長きにわたる付き合いだ。

「中川さんの畑がいちばん好きかもしれない。ほかの畑とは、やっぱりもう圧倒的に、ぜんぜん違うから。気持ちよさも違うし。
中川さんは、飄々とやってるように見えるけど、やっぱりテクニックがすごい。ただ『自然にやってます』ってだけで、ぐちゃぐちゃなのは嫌なんですよね。野菜でも卵でもなんでもそうですけど、材料が“ちゃんと仕事してるかどうか”が、カタネベーカリーでその食材を扱うかどうかの基準のひとつなんです。
なんか不思議なんだよなあ、中川さんって。スピリチュアルだけど、(過度に)哲学的ではないというか。かっこつけたライフスタイルとかでもないですよね。本質的なのかな」
toi

関西から移住し、敬愛する中川泰一さんの小麦畑のすぐ隣で開業した中西宙生シェフの薪窯パン屋。
「中川農場」や、「オフイビラ農場」など、地元十勝のオーガニックの小麦を自家製粉し、自家培養したルヴァン種で醸し、薪窯で焼き上げる。畑と森しかない場所にぽつんとたたずむ薪窯小屋は、パンの楽園に迷い込んだように錯覚する。
カタネベーカリーのスタッフもテンションが上がり、思わずたくさんのパンを買い込んだ。
「中西くんも、開業当初よりどんどんよくなってるんじゃないですか?パンもいいし、あのスタイルがハマってきたというか。自分がやりたいライフスタイルを、パン屋をやることで成り立たせてる。いいと思いますよ」

オフイビラ源吾農場

本別町にある有機生産者、篠江康孝さん。
甘さで定評のある品種キタノカオリのほか、アインコルンやエンマーのような希少な古代小麦もオーガニックで栽培。とくにブラックエンマーの穂は、羽を広げた黒鷲のようにかっこいい。
だが現代小麦の5分の1程度の収穫量にとどまり、年によってうまくいったりいかなかったりと、生産者泣かせのはずだが、「農場に来てくれたパン屋さんがよろこぶから」と栽培をつづけている。


「一番最初のとき、トラックの荷台にみんな乗っけて、畑に連れていってくれた。今年行ったらお嫁さんがいっしょに働くようになっていて、雰囲気が明るくなってて、すごくよかった。
僕らが見た陸稲(りくとう。田んぼではなく畑で育てる稲)の畑も、倒伏していて、とても収穫はむずかしそうに見えたけど、ハハッって笑っていた。とりあえずやってみる、なんでもトライする雰囲気がいいんじゃないかな」

しあわせチーズ工房

草を食む牛たちが眼下に見える緑の丘に小屋が一軒。
環境によく乳質もよい放牧酪農を営む「ありがとう牧場」のすぐ近くに立地、絞りたての生乳を使ってチーズを作る。
カタネベーカリー一行が訪れたとき、ちょうど本間幸雄さんはチーズ作りの真っ最中。大きな胴鍋に生乳を入れ、炊きながら撹拌する。チーズのできを左右する真剣勝負の背中を、カタネベーカリーの一行はみつめていた。その眼差しには同じ職人としての共感をはらんでいるようだった。


「本間君とはイベントで出会って、前から知り合いだった。でも、カタネベーカリーで使うようになったのは後から。もともと日本のチーズはあまりピンときてなかったんです。フランスのコンテとかのほうが、ぜんぜんおいしいと思ってたから」

「たまたましあわせチーズ工房のチーズをもらって、朝ごはんのときパンといっしょに食べたとき、(妻の)智子と『あ、おいしいね』って。それで、本間くんからチーズを取るって決めて、そっち(海外産)はやめたんですよ。
本間くんの、ストイックな姿勢もいいし。カタネベーカリーで使う材料には、なにか僕らなりの基準があるんだと思います。できれば国産がいいというのがあるし、知ってる人にお金を使えば応援になる」
津別

十勝から山また山を越えてやっとたどりつく、オホーツクの町・津別。
見渡す限り、風景のなかに人工的なもの、商業的なものがない。ただ緑、ただ畑、そして静寂。
清らかな空気感が片根さんの肌に合ったのか、津別の小麦生産者のもとへ、毎年通うようになった。
農家の「すばる」竹原宏太郎さん、「木樋桃源ファーム」鈴木健二さんらが、カタネベーカリー一行とバーベキューの火を囲むのが恒例になっている。
「津別の畑はすごく広い。山があって、川があって、麦があって。最初に来たとき、鈴木さんの義理のお父さんが言ったことが、すごく印象的でした。見えている山の色に、麦の葉の色を合わせると、いい麦が穫れるっていう。それ、すごくいいなと思って」

© katane Bakery
津別では、一貫して、甘さや、ミルキーな香りに特徴のある品種「キタノカオリ」を栽培。
普通は、小麦はほかの産地のものと混ぜられて流通する。
だが、すばる・竹原さんの願いは、自分の手塩にかけた小麦を味わってほしいというもの。その意を汲んで、津別限定のキタノカオリをカタネベーカリーが使いつづけてきた。長年の縁が実って、今年から津別産キタノカオリ(江別製粉)が一般販売されるようになった。
津別は、北海道のなかでも気候が冷涼。小麦の生育にはけっして好条件ではない。まして、栽培がむずかしいキタノカオリ。収穫前、湿った空気のなかでは、畑の中で穂についたまま小麦の粒が発芽して、粒を構成するデンプンが溶けだし、糖に変わる。それだけに、生地はつながりにくくなるが、ほかの産地にない特徴のある味になる。
「津別のキタノカオリを入れると、甘さが出ます。まあ、あとは自分がこれを使わなきゃいけないってなるじゃないですか。そうすると、いろんなパンに入れてなんとか使おうと思う。それがいいなと。
いろんなものからなんでも選べるって状況じゃなく、こっちが工夫しないといけない。縛りがある方がその麦のことが理解できる。津別を近くに感じてパンを作れるっていうのは、大きいですね」

© katane Bakery
小麦であれ、チョコレートであれ、レーズンであれ、洋酒であれ、スパイスであれ。パンに使われる材料のほとんどは、世界中から集まってきて、作り手の名前さえわからない。
だが、素材で心と心がつながり、作り手のいるところへ旅することができる国産の材料ならもっといい。
「行けば行くほど、だんだんその人とつながりが深くなってくる。それが楽しい」
片根さんたちは来年もまた北海道へと、畑を見て、たわいもない話をしに出かけるはずだ。





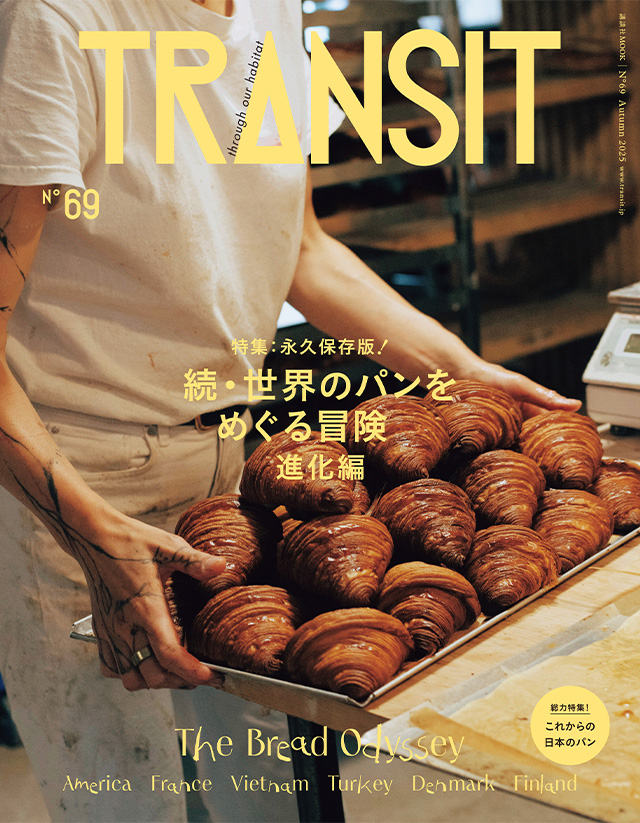


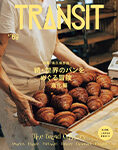








-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























