
月刊TRANSIT/80年目の平和への旅
READ
2025.08.26
20 min read
1945年8月15日、日本は敗戦を迎えた。焦土と化した都市、乏しい食糧、途方に暮れる人びと。そこから始まったのが、戦後という新しい時代だった。
長らく「奇跡の復興」「高度経済成長」といった成功物語で語られてきた戦後日本。しかし、その歩みを振り返れば、光と影、成熟と停滞の両面が浮かび上がる。
今回は、思想家・内田樹先生へのインタビューをお届けする。前編では、先生ご自身の戦後の原風景を起点に、この80年で日本が何を得て、何を失ってきたのかを語っていただいた。
高度経済成長がもたらした自由と豊かさの時代、1970年代以降に進んだ停滞と分断。そして、憲法をめぐる社会の空気や、大日本帝国をどう「供養」すべきかという問いまで──。戦後を生き抜いた一人の思想家の言葉から、私たちがこれから進むべき道を考えていきたい。
Interview&Text : AI TOMITA
Index
20 min read
戦後の原風景
──はじめに、先生ご自身が体験された戦後直後の東京について伺えますか?
僕が生まれた1950年は戦争が終わってまだ5年しか経っていません。まだ生産活動も消費活動も停滞していましたから、敗戦直後の瓦礫の広がる光景からそれほど変わってはいなかったと思います。
当時暮らしていた大田区下丸子のあたりには、軍需工場が建ち並んでいた工場街ですので、戦争末期にB29による空襲でほとんど破壊され、わが家は焼け残った神社の敷地内に建っていました。家の前の原っぱは野原ではなく、工場の跡地でした。遠目にはタンポポやレンゲの生える緑の原っぱですが、実際は焼けて折れ曲がった鉄骨やコンクリートの土台や散らばるガラスの破片を草が覆っていただけでした。人間の犯した戦争という愚行の残骸を小さな植物がけなげに覆い尽くしている。それが、僕にとっての戦後の原風景です。
75年の人生で見た、日本の成熟と停滞
──戦後80年という期間を、どのように振り返っていらっしゃいますか?
総じてよい時代だったと思います。なにより戦争がなかった。軍隊も特高も憲兵隊も隣組もなく、治安維持法もなかった。何を言っても、何をしても、誰かが暴力的に口をふさぐということがなかった。もちろん子供の頃は貧しかった。でも、それは関川夏央さんの言う「共和的な貧しさ」でした。貧しい人たちが助け合っていた。助け合わないと生きてゆけなかった。
その共同体も、東京オリンピックの頃までにはしだいに解体してゆきました。高度成長期に入り、どの家も豊かになると、家を建て直し、塀を建て回して、プライバシーを守るようになった。もう助け合わなくても生きていけるようになったら、共同体は要らなくなったのです。
それでも、1960年代に入ると、日本社会は自由になりました。敗戦のトラウマという心理的な「憑き物」が落ちたように、いきなり社会はワイルドでアナーキーで賑やかになりました。テレビとラジオが「何をしてもいいんだ」と大胆に活動領域を広げ、音楽も映画も演劇も文学も、あらゆる分野で新しい試みが行われました。僕はその時代にちょうど10代でしたので、ほんとうにわくわくするような気持ちで毎日を過ごしていました。
1970年代に入り、学園紛争やベトナム反戦運動が日本全土を覆った政治の季節が終わったあと、そういう明るさは翳ってきたように感じました。日本は1968年にドイツを抜いて世界第2位の経済大国になりました。国はどんどん豊かになっていったのですけれども、精神的な自由はそれ以前に比べると失われたように感じた。それは、人びとが「経済成長」という単一の国家的課題に専念するようになったからです。その甲斐あって、アメリカの背中に肉迫し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるようにまでなりました。
でも、その時代は僕個人にとってはあまりよい時代ではありませんでした。豊かになった代償に、人びとが「お金の話」しかしなくなったからです。そして、1990年代にバブルが崩壊し、それ以後が「失われた30年」と呼ばれるわけですが、僕の感覚ではすでに1970年代なかばから日本は「たいせつなもの」を少しずつ失い始めていたと思います。

大阪万博(1970年)
© takato marui
ですから、戦後80年を振り返ると、1960年代の終わりまでが「昭和が明るかったとき」であり、以後、経済的に豊かになるとシンクロして文化的な停滞が始まり、人心がすさみました。誰もがそこそこに豊かになれる時代だったから、自分の利益だけ考えていても、周りに迷惑が及ぶことはなかった。金儲けが下手な人間はただ「バカなやつだ」と見下げられるだけで、「そういう生き方をするな」と干渉されることはなかった。
でも、成長が止まり、パイが縮み始めると、人びとは急に周りを見渡して、パイの分配にうるさく口を出すようになった。「お前の割り前はこれだけだ」とか「オレの取り分に手を出すな」とか。組織のなかで「誰が生産性を下げているのか」「誰がフリーライドしているのか」をがみがみ言うようになった。人間が総じて貧乏くさくなった。市民として成熟することを止めて、全体に幼児化してきた。それが戦後80年を振り返った実感です。
時代とともに変わる社会の空気
──戦後日本は経済成長とともに社会が大きく変化してきました。そうした変化のなかで、戦争への向き合い方や憲法に対する議論は、どのように移り変わってきたとお考えでしょうか。
僕が子どもの頃、親や学校の先生たちはほとんどが戦中派でした。多くが天皇制や国家神道に対しては批判的で、天皇制は廃止すべきだと広言する大人たちも少なくありませんでした。でも、日本国憲法を悪く言う大人には僕は会ったことがありません。憲法は敗戦国民日本人が唯一誇りを持つことのできるものだったからだと思います。
かつて世界5大国の一角を占め、国際連盟の常任理事国であり、「アジアの盟主」を任じていた帝国が、する必要のない愚かな戦争を始めて、戦争に敗れて帝国は瓦解し、国家主権を失い、アメリカの属国に零落した。旧帝国臣民たちが敗戦で経験した喪失感と屈辱感は、戦後生まれの僕にはうまく想像できません。でも、だからこそ敗戦後の日本人が憲法にすがりついた理由は理解できます。
憲法9条1項は1928年に調印されたパリ不戦条約とほぼ同じ文言です。「国際紛争の解決のために戦争に訴えることを非とし」「国家の政策の手段としての戦争を放棄すること」という誓言に英米仏イタリアそして大日本帝国も署名しています。不戦条約は最終的に世界63か国が批准しましたけれど、それでも第二次世界大戦を防ぐことはできなかった。
ですから、本当に戦争を防ごうと思うなら、論理的には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」という9条2項が必要になる。理想主義で非現実的だと評される9条2項ですが、1946年時点ではこれが戦争を避けるためには必須の条項でした。
広島、長崎での原爆の被害規模が知れるにつれて、アメリカでは原爆投下を命じたトルーマン大統領に対する批判と核戦争に対する恐怖が同時に高まりました。ソ連が原爆開発を進めている以上、次に戦争が起こったら核戦争になる。第三次世界大戦が起きたら、人類は滅びる。どうやって次の戦争の到来を阻んだらよいのか。憲法起草にかかわったGHQのニューディーラーたちが思量したのは何よりもそのことでした。そして、彼らは近代市民社会のモデルを国際社会に適用しようと考えました。

昭和天皇とGHQのマッカーサー元帥、敗戦後初の会見(1945年9月27日)。
近代市民社会は、ロックやホッブズやルソーが理論化したように、「万人の万人に対する戦い」を止めるために、巨大な「リヴァイアサン」である国家・政府に理非判定の権力と実力を委ねるというものでした。「私人」たちの抗争を止めるために「公共」を立ち上げる。理非の判定は公共が下す。それに従わない私人は公共が実力を以て処罰を下す。
この仕組みを国際社会に当てはめようとしたのが、国際連合です。各国は自分たちの軍事力の一部、国家財産の一部を国際連合に供託し、国際社会に君臨する「リヴァイアサン」を創り出す。国と国の間で紛争が起きたら、この「リヴァイアサン」が紛争を調停し、理非を判定し、必要な場合は国連軍が出動して紛争を終結させる。そういう構想です。
近代市民社会が成立し、国民国家ができて、国民間の紛争は私闘によってではなく、司法が決着をつけることになった。これは否定しようのない揺るぎない歴史的事実です。だから、それと同じプロセスを国際社会に当てはめたらどうか、それ以外に核戦争による人類滅亡を防ぐシナリオはないのだから。これはごく「常識的」な推論だったと思います。
それに、9条2項はよく読むと「日本が国連軍に加わる」可能性を決して否定してはいません。国連軍が加盟国間の紛争を調停するために介入することは、公共的な行動ですから「国権の発動」ではありません。そして、国連軍の軍事行動は、警察が犯罪者を捕らえるために行う実力行使と同質のものと観念されているわけですから、これをある国が他国との間の「国際紛争を解決する手段」として用いる「武力による威嚇または武力の行使」と同一視することはできません。それは「私闘」ですが、国連軍の実力行使は「司法的介入」だからです。二者間の紛争であるか、そこに第三者である上位審級が介入するかによって、紛争のカテゴリーは変わります。
9条2項は、私人間の争いは「私闘」によってではなく、私人より上位にある公共による「司法的介入」によって解決されなければならないという近代市民社会のアイデアを国際関係に適用するために選ばれたものです。アイデアそのものはきわめて合理的だったと僕は思います。これからの国際社会のあるべき姿を世界に示したのです。

枢密院会議写真。1946年(昭和21年)10月29日、帝国議会において修正を加えた帝国憲法改正案を可決した枢密院会議の写真。
もちろん、GHQが「日本を軍事的に無力化する」という占領軍としての最優先の使命を果たすために9条2項を書き入れたということも事実です。でも、日本がいずれこの憲法の理念の通りの国になった時に軍事力によって国連軍に協力する道については、「国際紛争」という語の解釈の多義性に委ねた。そんなふうに考えることが可能ではないかと僕は思います。そんな憲法解釈をしている憲法学者がいるかどうか、僕は知りませんけれども、たぶん少数派であってもいるような気がします。
僕たちはこの憲法が制定されたあとに世界で何が起きたのかを知っていますから、このアイデアが破綻したことを前提にして、「9条2項は非現実的な夢想だ」と言うことができます。けれども、それは「後知恵」です。憲法制定時点においては、むしろ「1928年の不戦条約は非現実的な夢想だった」ということの方がシリアスな現実だったんですから。不戦条約の文言に何も書き加えないことの方がむしろ「非現実的で夢想的」だった。9条1項だけでは戦争は止められない。そのことは周知の事実だった。だからこそ2項が付け加えられたのです。
かつて9条2項がきわめて「現実的」なものだった歴史的時点が存在し、その時にこれは書かれた。ですから、この世界でもっとも先端的な、もっとも国際感覚にあふれた憲法条文を持ったことは、敗戦後の日本人にとって誇りでした。当時の日本人が「世界一」だと誇れるものは、この時点では日本国憲法しかなかった。だから国民は歓呼の声でこれを受け容れたのです。僕の世代に「憲男」とか「憲子」とかいう名前が多いことからもその期待の大きさは知れると思います。
僕が知る限り、1960年代まで、憲法について、これを「恥ずかしい憲法」だとか「非現実的」だとか言って批判する人はいませんでした。改憲が声高に語られ始めたのは、戦後ずいぶん経ってからです。それは原爆投下以後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争と戦争はたくさんあったけれど、一度も核兵器が使われなかったからです。これからも戦争はつづくだろうけれども、どうやら核戦争は起きそうもないという楽観が改憲論の前提にあります。「戦争ができる国になりたい」という改憲派の願望は「日本が核兵器で攻撃されることはない」という何の根拠のない予測を前提にしています。日本だけが過去に核兵器での攻撃を受けたという現実があるのにもかかわらず、どうしてこんな楽観が抱けるのか、僕には理解不能です。

© ©︎Syced
──日本国憲法を支持する風潮が当たり前だったんですね。
1960年代まではそうでした。学生運動の時代でも、革命についての空想的な議論はさかんにされましたけれど、「日本国憲法をどう変えるか」というような議論はまったくなかった。「革命をするぞ」と言っている人間が今ある憲法の個々の条項の是非なんか論じるはずがないです。
そして、政治の季節が終わると、今度は時代の空気は金儲け一色になった。もう政治のことなんかどうでもよくなった。実際、21世紀になるまで、誰が総理大臣であるかさえ僕はろくに知りませんでした。何より、当時の政治家たちは全員が戦争経験者で、「二度と戦争はしない」という点では共産党から自民党まで一致していた。そして、国家目標は「国民一丸となって経済成長をめざす」で統一されていましたから、ベトナム戦争が終息したあとは、国民は政治に無関心でいられた。
状況が大きく変わったのは、21世紀に入って10年経ち、維新が大阪で勢力を伸ばし、民主党政権が瓦解し、さらに東日本大震災を経て始まった第二次安倍政権からです。それまでは僕も大阪市の平松邦夫市長から特別顧問を委嘱されたり、民主党政権の鳩山由紀夫総理大臣に教育について政策提言をするように求められたことはありました。だから、自分の考えていることが政治に生かされる回路がありました。
でも、第二次安倍政権が発足して2、3年してから、公的なところから僕に意見を求めるということがぱたりとなくなりました。それまでは内閣調査室のレポート作成を手伝ったり、自衛隊に呼ばれて講演することさえあったのに、それが全部止まった。なるほど、日本政府は僕の意見を聴く気がないのだということが身にしみてわかりました。向こうに「お前の意見なんか聴く気がない」と言われると、こちらも意地です。僕がメディアで積極的に政治的発言をするようになったのはそれからです。実はこの10年ほどのことにすぎないんです。
大日本帝国をどう“供養”するか。いま日本に問われていること
──改憲をめぐる動きが注目を集める今こそ、戦後の出発点を問い直す必要があるように感じます。敗戦は、人びとにとってどのような喪失や断絶を意味したのでしょうか。
小中学生くらいで敗戦を経験した人びとは、当時みな愛国少年少女でした。大日本帝国のために殉じることに何のためらいもない、そういう子どもたちだった。それが、8月15日でいきなり「これまでお前たちに教えられてきたことは間違っていた」と言われて、過去を捨てろと言われた。教科書に墨を塗った世代のトラウマを僕たちは簡単には想像がつきません。彼らはいわば戦前の日本に下半身を残し、戦後の日本に上半身が乗り出しているというような状態でした。
大人たちは「戦前の下半身は斬り捨てろ」と命じるけれど、そんなことはできるはずがない。それまでの時代に子どもたちなりに信じたものがあるし、愛したものがあるし、感動したものがある。それを全部「捨てろ」と言われても簡単に「はい」とは言えません。ですから、その世代の人たちの中には戦前に残した半身と戦後の半身の切れ目を縫合しようとする人たちがいた。吉本隆明や江藤淳はそういう人だったと思います。
例えば、吉本隆明の「大衆の原像」という概念は、彼が子どもの頃に佃島の町内で見ていた職人や商人たちの「自分なりのプリンシプルを持ち、きちんと一本筋を通して生きている」帝国臣民たちへの郷愁を伝えています。
戦後の日本人は、どこかで職業的な気骨や、市民としての自己規範を失い、ただ金儲けだけにしか興味のない情けない存在になってしまった。そういう同時代に対する違和感を通じて、戦中派の人たちは戦前の日本にあった「よきもの」を救い出し、それを戦後社会に接合するために、さまざまな個人的な工夫をした。僕たちの世代には「戦前に遺した半身」はありませんけれど、この世代の思想的営為には深い親しみと敬意を覚えます。

1960年の安保闘争。
──戦後という時代を支えたのは、そうした手探りの営みだったんですね。
僕はこの年になって、自分に託された仕事は「大日本帝国をどう供養するか」ということだと考えるようになりました。ただ否定するのではなくて、きちんと供養しなければならない。供養というのは、法事に集まった人たちがするように、「故人について、ひとりひとりが知っていることを物語ること」です。それに尽くされる。
『日本のいちばん長い日』という映画の中に、陸軍省でポツダム宣言の受諾が決まったあと、次々と書類を燃やす場面があります。そのときに井田中佐(高橋悦史)が「大日本帝国の葬式なんだから、どんどん燃やせ」という言葉が出てくる。先日何度目かに観た時に、この台詞が僕のなかにずっと残っていたことに気がつきました。
8月15日には大日本帝国の葬式だけは出した。「死にました」という告知だけはした。でも、まだ供養は終わっていない。市ヶ谷台の陸軍省の書類をいくら焼いても「大日本帝国の供養」は果たせない。きちんと供養していないと、死者は甦って祟る。戦後80年経って、レイシズムや、外国人排斥や、「大東亜戦争賛美」のような戦前回帰的風潮が出てくるのは、大日本帝国をきちんと供養していないからです。
あれは「祟り」なんです。大日本帝国の幽霊なんです、あれは。「ちゃんと供養してくれ」という死者の懇願をひさしく抑圧してきたせいで、あのような畸形的なかたちで症状化してくる。

中央線・高尾行きの国鉄電車の車内にて(1960年11月頃撮影)。
© Charles Dunn
供養するというのは、語るということです。それだけです。どんな国だったのか、どんな人たちが暮らしていたのか。何を生み出したのか。何を破壊し、何を失ったのか。それを中立的な立場から、平静に、できるだけ詳しく語ることです。
僕は先般権藤成卿という人についての研究ノートを出版しました。昭和維新の思想的指導者として北一輝と並ぶ人です。彼のアジア主義は、結果的には大日本帝国の朝鮮半島併合や満州建国という植民地主義を正当化する思想になりました。功罪を計れば創造したものより破壊したものの方が多い思想家かも知れません。でも、権藤自身が構想していた東アジア共同体は同胞的な連帯で結ばれた、おおらかなもので、決して帝国主義的なものではなかった。
明治人の構想したアジア主義は、定義しがたく、とても一言で言い切れるものではありません。日韓併合はたしかに植民地主義的な侵略ですが、その前段階には、日本と朝鮮の人たちが合議を重ね、どうすれば兄弟的な連帯を築けるか真剣に模索した時期も存在したのです。その日朝双方の活動家たちの夢が裏切られて、日韓併合という凡庸な植民地支配のシステムが出来上がった。それでも、こうした歴史的事実を「結果的に日韓併合に流れこむ文脈にあったことだから、すべて悪だ」と言って斬り捨てると、それはあとに祟ります。過去の日本人がしたことは、まともなことも、ろくでもないことも、できるだけ掘り起こして、後世の人たちの前に手を加えずに差し出して、その上で、一人ひとりの日本人が自分で、自力で、その意味を判断して欲しいと思います。人びとの前に「こういうことがあったんです」と物語ることそれ自体が供養になる。きちんと供養すればもう過去は祟らないのです。

© NAGASAKI CITY
歴史をめぐる対話を可能にするために
──分断が進む社会において、異なる立場の人びとと対話を続けることは日々難しくなっているように感じます。先の大戦を供養するために、私たちはどのように語り合うことができるでしょうか。
難しい仕事だと思います。ただ必要なのは、まず「歴史的事実」についての共通理解です。つまり、「こういうことがあった」という事実関係だけは、対話の土台として共有しなければなりません。南京虐殺がなかったとか、日本のアジア解放を現地の人は今も感謝しているとかいう歴史の歪曲は止めて欲しい。事実そのものを否定してしまえば、死んだ帝国を供養することはできません。
では、どんな本を読んだらよいか。「供養する」ことを目的にして書かれた本を読むといいと思います。司馬遼太郎、半藤一利、保阪正康の本をまずお薦めします。実際に現場にいた人たちの証言を聴き、膨大な史料を丹念に読み解いてくれています。事実として「これだけは共有できる」という最大公約数的な歴史認識を持つこと。それが供養になります。それから文学です。戦争について書かれた文学作品は、吉田満の『戦艦大和ノ最期』も、大岡昇平の『レイテ戦記』も、野間宏の『真空地帯』も、大西巨人の『神聖喜劇』も、村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』まで含めて、それを読むことそのものが供養の一部になると僕は思います。
もちろん、いまの右翼や左翼の人たちに向かって「あなたの歴史認識を変えてくれ」とは言いません。もう思想が凝り固まった人に言っても、たぶん僕の言っていることの意味は通じないでしょう。でも、まだ日本の歴史をどう見るかについて態度を決めていない人たち、未決定状態にある人たちにはできれば「大日本帝国の供養」のお手伝いをして頂きたい。
そして本当を言うと、過去については「未決定」という状態を続けて欲しいのです。知識を得て、歴史認識が厚みのあるものになればなるほど、自分の政治的立場を簡単に決めることができなくなります。未決定とはそういうことです。でも、僕はそれでいいと思います。毎回選挙のたびに頭を抱えながら「どこに投票したらいいかわからない」と困惑する。僕はそれこそ成熟した有権者だと思います。
Profile
内田樹・うちだたつる
1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。
1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

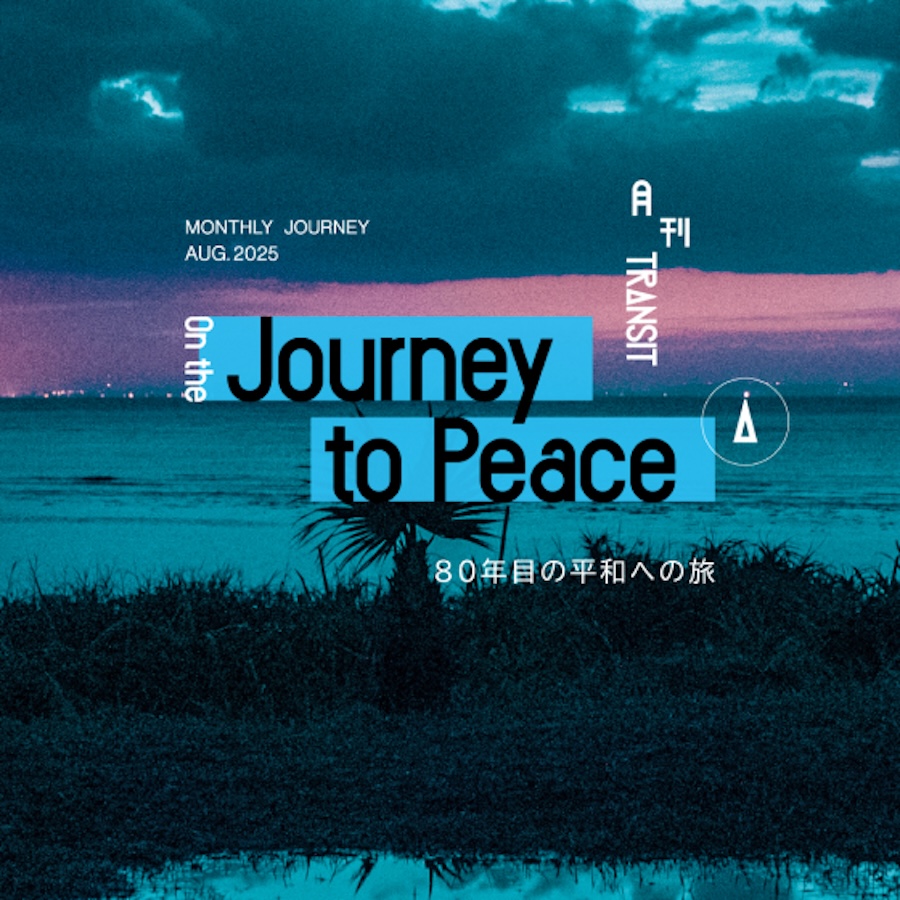
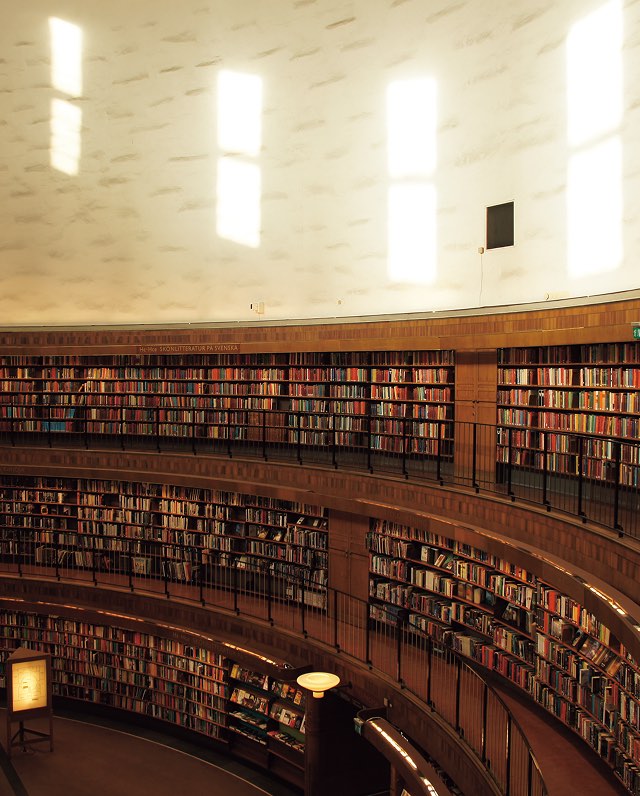
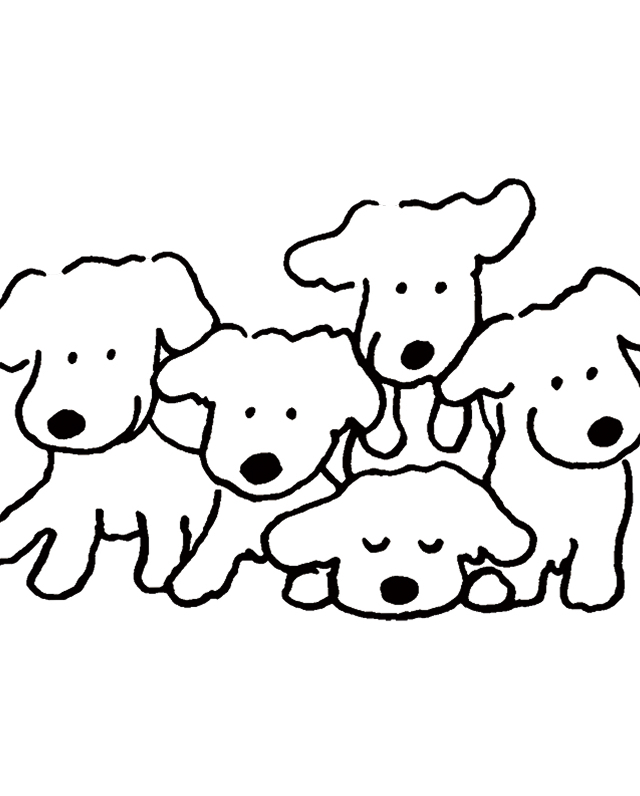






-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























