
中世にキリスト教の三大聖地となり、今も多くの人を惹きつける「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」。歩くことで見えてきた「星に導かれた道」について、「まなぶ」「準備する」「旅する」「話す」の切り口で見つめ返した。
「話す編」では、サンティアゴ巡礼路で偶然と必然に導かれて出会った仲間たちの声に耳を傾けた。
Photo & Text : Mikito Morikawa
巡礼の仲間たちと交わした言葉
サンティアゴ巡礼路では、一つの目的地に向かって歩くなかで多くの旅人に出会う。人によって出発する時間、休憩するタイミング、歩く距離などは異なるが、同じ道を歩いているために再会する確率は高い。
生活のリズムや価値観が似ている旅人とは何度も出会うことになり、似たものを共有しているから話もはずみやすい。また、約束したわけではないが、バルや巡礼宿(アルベルゲ)での偶然の出会いが重なって親しくなることも。一緒に歩いてさまざまな話をし、「Buen Camino! See you again on the road!」と言って別れる。
巡礼路での出会いは偶然の要素もあるが、同じ道を歩くなかでの再会や、そもそも巡礼路を歩こうと思った志を共有している点では必然の要素もある。ここに紹介するのは、そんな偶然と必然に導かれて出会った仲間たちだ。

プエンテ・ラ・レイナへ向かう途中で出会った地元のおじさんは、石を積み上げるのが日課だ。ジェンガのように一つひとつの石をバランスを取りながら積み、小さな石を挟み、「今日はここまで」と思うまで作業は続く。翌日にタワーが残っていれば、また崩して石を積み直す。その繰り返しのなかに、道を通る人やその土地への祈りが込められている。“日課”を終えると、上半身裸のスタイルで10kmほどの散歩を続ける。
横で見守っているのはポーランドの大学で社会学を研究しているピーター。一人になる時間を持ちたいと、時々寝袋で野宿をするなど自分のスタンスで旅を続けていた。今回の巡礼旅を経て、サンティアゴ巡礼路について論文を書きたいと考えているとのこと。

見るからに山スタイルのかっこうをしたオランダ出身のステフィー(左)とフランス出身のリリアン。人を包み込むような温かさに溢れたふたりは、フランスの道ではなく、GRと呼ばれるトレッキングルートを歩いている途中でサン・ジャン・ピエ・ド・ポーに立ち寄った。GRはアップダウンがかなりあるが、標高が高いのでフランスの道よりも涼しいという。また、フランスの道よりもマイナーなため、トレッカーたちはより親しくコミュニケーションするのだとか。
サンティアゴ巡礼路にしても、GRにしても、ルートが整備されていることで多くの人に歩く動機を与えている。素晴らしい出会いや学びをもたらす歩く旅の機会が広く開かれていることが、社会に成熟した豊かさをもたらしている。

アメリカ、コロラド州に暮らす、住宅建築のビルダーであるマイケル(左)と看護師のキャシー。ピレネー越えの途中で、チョリソー、ワイン、パンのピクニックランチを楽しんでいたふたり。イタリアで娘の結婚式に参加した後、結婚1周年という節目に巡礼路を歩くことにした。長い巡礼の途上、話し合って別々に歩くこともあったという。ふたりで歩くことの楽しみ、一人で歩くことの愉しみがあると語る。
写真を撮ったことがきっかけになり、次の目的地まで一緒に歩いた。山を降りる途中に危険な近道と安全な遠回りの道との分岐点があり、巡礼事務所では安全な道を歩くように勧められたのだが、彼らはガイドブックなどを調べて近道を選択。簡単に“権威”の指示に従わず、自分たちが考える“正しい”道を選ぶところに、かの国の“パイオニアスピリット”を感じた。

休憩するたび、おいしそうにタバコをふかすクリスチャンはドイツ出身で、ギムナジウムでラテン語と政治・経済を教えている。ギムナジウムはエリートコースの中等教育学校だが、その先生になるのも大変で、彼の場合は大学で7年間勉強して2年間教育実習をしたという。これまでポルトガルの道、プリミティボの道を歩いたことがあり、今回は教員試験に合格後、初めてフルタイムの教師として働きはじめる前の期間を利用してフランスの道を歩いた。

ニューヨークの高校でアメリカ文学を教えているフランシス(左)と、スペイン、バレンシアの高校で英語を教えているビンセント。フランシスは毎年夏休みの度に世界のさまざまな場所を訪れていて、新しい学びを続けている。お母さんが病気で入院しており、いつも家族と連絡を取り合いながら旅をしていた。
ビンセントは若いときにロンドンで4年間暮らし、バーテンダーなどいろいろな仕事をして英語を学び、その後にスペインに戻って教師になった。生徒には、一度はスペインを出て新しい世界を見ることを勧めているという。
私たちが食事をしたレストランは、約35万年前まで遡る人類の祖先の人骨が発見されたことでも知られるアタプエルカにあるRestaurante Comosapiens。ランチコースは22€で、クオリティを考えると欧州ではリーズナブル。

ニューヨークで看護師をしているゾーイ(左)とシカゴで高校の教師をしているタイラー。シカゴ出身のふたりは高校時代からの親友で、今回休みを合わせて巡礼路を歩いていた。常にオープンかつフレンドリーで、2人の周りにはいつも人が集まっていた。歩きながらも「今度はあの巡礼路に行こうね!」と相談していて、一生ものの友情はうらやましい限り。
今回の巡礼旅を通して多くの教師に出会ったが、教える立場という権威に甘んじることなく、常に旅をして学び続けている姿勢が心に残った。旺盛な好奇心を持って学ぶことやチャレンジを続けている教師の後ろ姿は、なによりも雄弁に生徒に学ぶことの喜びを伝えられるのではないか。
また、巡礼路が教会関係者、ボランティア、理解ある地元の人など多くの存在によって支えられているだけでなく、巡礼者においても教師、医療関係者、カウンセラーなど、人や社会のために働いている人が多い印象を受けた。歩きながら多くの人の善意にふれられることも、巡礼旅が特別な経験となりうる大きな要因だ。

デンマーク出身のサンドラは巡礼路を歩く直前は、ヒマラヤのトレッキングルートを旅していたという。以前は、ヨットで長い航海も経験し、海で想定外の事態に見舞われるなか仲間たちと協力しながらセーリングを続けたという。若いうちはなるべく海外を旅していろんな経験をしたいという彼女は、現在は学校の受付などを含めてパートタイムの仕事をしていて、旅行資金を貯めるのに十分な賃金を得ているという。
セーフティーネットが整うデンマークの社会システムがあるからこそ、自由な生き方を選択することができるわけだが、旅でのさまざまな経験のなかで成熟した人間が育っていくとしたら、社会システムとして十二分にワークしているのではないか。

イラン出身のエリナ(左)と、彼女の友人でパレスチナ出身のタレック。エリナはロンドン大学東洋アフリカ研究学院でグローバルディベロップメントについて勉強している。ふたりは恋人ではないのだという。男女の友人で旅をするケースは日本ではわりと珍しいかもしれないが、とてもクールに映った。

イギリス出身のミシェル(中左)は長くスペインに暮らしており、パンプローナの一つ先にあるシスルメノールで自宅の一部を改装してQuiet light room!(宿情報は巡礼路アプリのBuen Caminoからアクセス可能)という巡礼宿を経営している。特にパンプローナでサン・フェルミンの祭が開催されている期間中はパンプローナの宿料金が急騰するので、近郊の街に泊まるのがおすすめ。ローカルバスに乗ればパンプローナへ簡単にアクセスできる。
娘のアンバー(中右)、Quiet light room!に宿泊していたベルギー出身のデュリュス(左)、ウェールズ出身のクレア(右)と連れ立ち、サン・フェルミンの祭りにやってきていた。デュリュスもサンティアゴ巡礼路を歩いたことがある。きっかけは祖父が巡礼旅の最中に亡くなったことだという。今回は仕事のギャップ期間中に車でスペインを旅していた。

サン・フェルミンの祭りに家族や友人と来ていた地元の人たち。若者は友だち同士で、子どもや親は家族で、それぞれ年に一度の祭りを満喫する。大人から子どもまでが毎日集まって、7月6日から14日まで街のあちこちで行われるさまざまなイベントに参加する。祭りにはパンプローナ市内だけでなく近郊の人も参加するので、ローカルバスは白と赤の衣装に身を包んだ人でいっぱいに。

パンプローナ市内にあるファーストフードで働いていたレイリ・パトゥ(左)とマウリシオ。祭り期間中は、働いている人も白と赤に身を包む。

台湾出身のジムはゲームデザイナーとして働いていたが、若いうちに広い世界を見たいと旅をしていた。今年の秋はお遍路を歩いて、冬は長野でスノーボードのインストラクターとして働き、来年はワーキングホリデーを使ってロンドンで暮らす予定。
父親は台湾で開業医をしているエリート一家だが、父親は長時間労働もあって一時重い病気を患っていたという。それゆえ、健康でいること、好きなことをして生きることをの大切さをジムに語っているという。社会の物差しではなく、人生で何をやりたいのかを考える流れは、東アジアの国々でも広がっていることを実感した。

韓国出身のステラ(右)はベトナムのハノイにあるアメリカンスクールで勉強している。卒業生の半分ほどがアイビーリーグに行くといい、成績が悪いと退学もあるハードな環境のなかで高校生活を送っている。両親の期待もあり、有名な大学へ行くプレッシャーは大きい。そんななかで自分を見失っていると感じ、自分は何をやりたいのか、自分にとって何が大切なのか確かめたいと巡礼路を歩くことに。彼女と同伴する形で母親のマリア(中)も一緒に歩いていた。
巡礼途上でふたりに出会ったというミン(左)も韓国出身で、以前に韓国軍の特別部隊に所属していたエリート。その後は保険会社で仕事をしていたが、あまり意味を見出せず、また大変な時間を過ごしたことで、巡礼路を歩くことにしたという。次のステップとしてフランス外人部隊で働いた後(5年働くとフランス国籍を申請できる)、ヨーロッパのどこかで巡礼宿を経営するのが夢だという。ミンと私がアルベルゲに泊まったとき、偶然に同室になったのがフランス外人部隊で教官をやっていた人で、ミンは連絡先をさっそく交換していた。世界に広がるサンティアゴ巡礼路ネットワークが功を奏しますよう!
韓国はクリスチャンの数が多く(プロテスタントとカトリック合わせて全人口の27.6%)、韓国の三人も台湾のジムもカトリックで、ときどきミサに参加して祈りを捧げていた。韓国も台湾も日本にひけをとらない学歴社会で、社会の格差も拡大している。そんななかで生き方をあらためて見つめ直そうとしている隣国の仲間と出会えたことは自分にとって大きな宝物だ。

中国出身のリーチャオはロンドンの王立音楽大学でピアノを学び、現在は中国の大学でピアニストをめざす生徒たちに音楽を教えている。もともとニュージーランドでプログラマーをしていたが、キャリアチェンジした異色の経歴。名門の音楽大学に入学した理由もユニークで、ピアニストをめざす同国の生徒たちを見ていてプロは目指さず、教える道に進もうと考えたからだという。
巡礼路を歩いているとき音楽を聴くことはあるのかと聞くと「音楽は聴かないけれど、歩いているとき頭のなかで音楽が流れている」という。朝はハイドン、午後はショパンやラフマニノフなど、ムードによって浮かんでくる曲は変わるとか。歩く情景とピアノが混ざり合う彼の巡礼旅とはどんなものなのだろうかと想像力を刺激された。

イタリアから自転車の旅をしていた家族が、パンプローナとプエンテ・ラ・レイナの間にある峠の上に設けられた巡礼者のモニュメントの前で記念撮影していた。欧州では自転車レースの人気が高く、自転車で旅をする人が多い。巡礼者においても、歩行者だけでなくサイクリストもよく見かけた。ロードバイクの場合は自動車道を走ることになるが、マウンテンバイクやクロスバイクであれば場所によっては歩行者と同じでこぼこ道を走ることもある。

スペイン出身のセルヒオは歩いている途中で拾ったものをコラージュした杖で巡礼旅を続けていた。作家性の高い映画の巨匠監督にも造詣が深いアーティスト気質の学生だ。母親の姉が危篤になったときは、回復を願って友人と一緒に24時間寝ずに100kmほど巡礼の道を歩いたこともあるという。何枚か写真を撮らせてもらっていたところ、マーベルのスーパーヒーローさながら「一つ目のサンティアゴマン」に変身してポーズを取ってくれた。

ドイツのケルン出身のノアは高校を卒業するとすぐに南米をバックパックで旅したり、ネパールのアンナプルナサーキットを歩いたこともあるなど根っからの旅好き。今回は仕事の休みを利用して2週間ほど歩いていた彼女は、ログローニョからナヘラへ向かっていたときに靴が合っておらず足を痛めてしまったという。ただ、途中で見つけた靴(巡礼者は不要になったものをほかの人のために置いていくことがある)が足にフィットしたので巡礼を続けることができたそう。そんな小さな“幸運”も巡礼の道ではよく起きる。

犬と一緒に旅していたドイツ出身のカイは、オリーブ畑のあるポルトガルの家を出てローマまで向かうため、フランスの道を私とは逆に歩いていた。秋までにローマへ辿り着き、その後はオリーブの収穫をするためヒッチハイクをしてポルトガルへ戻る予定だという。彼は時にスタンプを売ったり、フリーハグをして人とコミニケーションを取ったりして巡礼を続けていたが、あまりお金を持っていないようだった。
そのとき私は韓国人のミンと一緒に歩いていて、カイが私たちと会話するときの表情は喜びに満ちているように見えた。最後に彼が私たちにステッカーをくれたので、「少ないお金ですが」と言い添えて2ユーロを渡すと、彼は礼を言ってお金を受け取った。そこにはお金を持たないことへの卑屈さはなく、むしろ資本主義社会と一定の距離を取りながら自分のスタンスで生きていることに裏打ちされたしなやかな強さを感じた。誰か別の人が通った道を辿るほうが楽に違いないが、彼は道を外れて歩く勇気を持っているのだ。
サンティアゴ巡礼路を歩く人は、少しだけ“人生の道”を外れて自分を見つめ直そうとしている人が多いが、そうはいってもサンティアゴ巡礼路には多くの道標があり、それに辿って歩いていけばやがて目的地に辿り着くことができ、完歩した暁には証明書までもらえる。そして、それぞれの道に戻っていく。ただ、巡礼路を歩いていると道を外れるどころか、道を”逆走”するような人に出会うこともある。そんな出会いが、巡礼者をさらに迷わせ、巡礼の旅をより深いものにしてくれる。巡礼路では誰もがある種の迷いを持ちながら歩いているからこそ、お互いに影響を与え、お互いに学び合い変わっていくことができるのかもしれない。

アメリカの西部劇に登場するスモールタウンを思い起こさせるフロミスタでAlbergue Luz de Frómistaというアルベルゲを経営するガブリエルは元々絵描きをしていた。宿には彼のオリジナルのものから名画の模写などさまざまな絵画が飾られている。彼が白と黒のグラデーションだけで描いた教会内部のパステル画は、静謐な祈りの場所の雰囲気が満ちていた。
オランダ人の女性と結婚して、長くオランダに住んでいたが、20年ほど前にふたりでサンティアゴ巡礼路を歩いていたことがきっかけで、オランダからスペインへ移住し、今はアルベルゲを経営している。アルベルゲの仕事で忙しいので、今は絵を描いていないという。「サンティアゴ巡礼路は人生を変えてしまうほどパワフルなものだよ」と、現在の生活に対してまんざらでもない表情で言った。

アイェグイにある鍛冶屋のForjas Ayeguiでは、ふたりの職人が巡礼者のためのお守りをはじめさまざまな金属加工品をつくっていた。金属を加工するための火は薪を燃やして起こしており心地よい香りがする。旅のおみやげを探すにはぴったり!

マリサはエル・ブルゴ・ラネロで小さな食料品店La Tiendina del Solを切り盛りしている。私がお店に入りトイレを借してほしいとお願いすると親切に対応してくれた。地元の人たちとの会話を大切にしていて、彼らからも親しまれていることが伝わってくる。
彼女は体調の問題で長いこと子供ができず、医者からも難しいと言われていたという。その後で夫と一緒にサンティアゴ巡礼路を歩き、1年後に息子が生まれた。それは彼女にとって巡礼路がもたらしてくれた“奇跡“であり、巡礼路に恩返しをするべくこの街で店を開いて、巡礼者に対してもサービスをしているという。
サンティアゴ巡礼路では、世界や人生を少し変えてしまう小さな“奇跡“に何度が出会った。巡礼路においては何かを信じることが当たり前のこととして受け入れられているから、そんな物語がいろいろな場所で生まれるのかもしれない。

メリデの少し前の街で教会で出会ったベトナム出身のトランは、グラナダにある教会付属の大学で神父になる勉強をしている。夏の間はこの教会に手伝いに来ていて、巡礼者のスタンプを押したり、話し相手になったりしていた。
彼は仏教の影響も深く受けていて、アジア人として神父になる道を選んだことに葛藤を覚えないわけではないと話す。また、大学での勉強や生活は苦しいこともあるという。ただ、キリスト教の信仰があるため、スペインでアジア人として生活していても現地の人々とのつながりを感じられるという。私が巡礼路を歩いて感じたことを話したり、アジア人として欧州で暮らすことの見えない壁について共感することがあると話すと、今ここでお互いの内面についてシェアリングすることができてうれしいと言ってくれた。
神父になった後、世界のどこへ赴くは教会が決めることになる。カメラをまっすぐに見つめる瞳には、厳しいが自分の信じた道を生きることを決めた強さが宿っているように感じた。彼自身も写真を撮るのが好きで、いつかカメラを買って撮影を楽しみたいという。

レオンの手前にあるレリエゴスという小さな街に到着して、夕方に散歩をしていたら、家の前で夕涼みをしている親子に出会った。90歳になる母のエネディーナを、息子のフランシスコがいわたりながら扇子でやさしく扇いでいた。スペイン北部では日が傾き始めると、気持ちのいい風が吹き始め気温が下がる。家にこもるのではなく、外に出て気持ちのいい風に当たったり、街の人と短い会話をすることがとくに高齢者にとって大切であることを知っているのだろう。
スペインでは、人が街に出て広場で語り合ったり、一人でたたずんでいたりすることが当たり前の風景としてある。とくわけ夏場は夜遅くまでにぎやかだ!どんな街にも広場があり、そこに水飲み場やベンチがあって、人が心地よくいられるようデザインされている。また、水飲み場やベンチは巡礼者のような外の者に対してもありがたい存在だ。前出の教師をしているビンセントは、スペインでは家にこもってデジタル空間で長い時間を過ごすことが比較的少ないのではないかと語っていた。人生を楽しむことについて世界トップクラスと言われるスペイン人だが、その秘訣はいろんな人と出会い、時間を共有することにこそあると考えているのかもしれない。

私が風邪を引いて3日間お世話になったレリエゴスの巡礼宿Hostel La Paradaを切り盛りしているのは、ナイスガイなエセキエル(左)とファンキーなデビーの夫婦だ。ふたりは巡礼路のシーズンである春から秋まで宿を経営し、オフになる11月頃には宿を閉めて地元のマヨルカ島で暮らす二拠点ライフを送っている。
デビーは20歳になる息子をベイビーと呼んでいて、理由を聞くと「私にとってはいくつになってもベイビーなのよ!」とのこと。ふたりで料理もつくっていて、おいしいスペインの家庭料理が楽しめる。地元の人もバー&レストランとして立ち寄っていく。

メリーデにあるO Candil Hostelのオーナー夫婦も3月から10月まで宿を経営して、冬時期は旅に出るのだという。ギャビー(左)は建築を勉強していて、宿のイラストなども彼女が描いている。スソは以前はイタリアでガリシアの語学、文学、文化を教えていた。彼は現在52歳で、65歳になったらリタイアしていろいろなところを旅する計画だという。
彼ら自身が旅人であるから宿も旅人目線でデザインされていて、とても気持ちよく滞在できた。旅することを愛し、旅人として自由に生きることを年齢に関係なく実践していることに憧れを感じ、刺激を受けた。サンティアゴ巡礼路では、巡礼者だけでなく、巡礼路を支えている多くの人においても、人生をとことん楽しもうとしている人びとに多く出会える。

オスピタル・デ・オルビゴにあるALBERGUE SAN MIGUELの前で雑談をしていたふたりは、夫婦ではなく近所の知り合い。ふたりのポーズと表情に、小さな街に長く住む間柄の親しい関係性が現れている。花が飾られた街並みや色使いがおしゃれいなふたりの服装からも、スペインのスモールタウンが持ち合わせる明るさやかわいらしさが伝わってくる。
街を通りかかったとき、Hola!と挨拶したり、写真を撮らせてほしいと話しかけると、ほとんどの人はフレンドリーに応じてくれた。巡礼路で立ち寄る多くの街は、数百人、数十人が暮らす小さな集落だ。そこで暮らす人びとにとって、彼らの日常を通り過ぎていく世界中からやってくる巡礼者たちはどんな存在なのだろうか。そのことについて地元の人とじっくり話す機会はなかったが、それらの街を巡礼路が偶然にも通ったことで、地元の人びとが巡礼者を何百年にもわたり見守ってきたことはまぎれもない事実だ。

アストルガへ向かう途中、午後4時を回って気温は31度まで上がり、私は疲れ果てていた。どこか木陰で休もうかと思っていたとき、Google マップに休憩所のマークを発見し、そこまで歩いてみようかと歩みを進めた。ようやく辿り着いたEl Jardín del Almaと呼ばれる場所は、巡礼者にとってオアシスのような場所だった。
そこにはフルーツや飲み物やクッキーなど、ご馳走が並んでいた。スタッフらしき人もいるがおしゃべりしたり本を読んだりして、特別に世話を焼く感じはない。私は自分でオレンジを切り、絞り機で絞って喉を潤した。オレンジだけでなく、プラムやぶどうなど、どれも格別に甘く、水分をたっぷり含んでいた。近くの農場で収穫されたからだろう。
すべての食べ物は巡礼者のための施しとして用意され、ソファもあるので休憩しながら旅の話に花を咲かせることもできる。ささやかなお金を寄付してから、そこにいた男性に声をかけると「15年前に私がここを始めたが、今は別の者が引き継いでいて私はたまに立ち寄るだけ。ここはみんなのためにみんなでつくった場所で、君もその一人だ」という。
お礼を言ってその場を離れる際、Buen Caminoと馴染みの言葉をかけてもらった。「みんなのための場所をみんなでつくる」という言葉を反芻しながら、El Jardín del Almaだけでなく、サンティアゴ巡礼路も一人ひとりがつくっていくものなのだろうと感じる。El Jardín del Almaに立ち寄る前にずいぶんと長く感じられた次の街までの道のりは、もう歩くのが苦痛ではなかった。300kmを切り残り2週間ほどとなった旅路において、サンティアゴ巡礼路の真髄にふれた気がした。

オーストラリア出身のデビッドは78歳。今回出会った巡礼者のなかで最高齢だ。フランスの道の起点となるサン・ジャン・ピエ・ド・ポーから歩いている彼は、長くジャーナリストとしてニュースやテレビ映像の制作をしてきた。彼はいっさいデジタルツールを使わないので、撮らせてもらった写真を送ることはできない。ただ、彼は「それで良いのだ」と言う。デジタルツールを使わないのは溢れる情報に振り回されたくないからだ。見せてもらったノートには巡礼路についてのメモがびっちり書かれていた。今回の旅をまとめて本として出版する予定だという。

今回の巡礼旅で出会った唯一の日本からやってきた巡礼者である梅澤凜太郎さん(左)と恵美子さんは、孫と祖母。恵美子さんは最初に夫とサンティアゴ巡礼路を歩いてはまったそうで、今回が3回目。親子で歩いている巡礼者には何度か出会ったが、祖母と孫は初めてだ。なんと素敵な旅人関係だろう。凜太郎さんは大学3年生で、初めてとなる今回の巡礼はビアフランカからサンティアゴ・デ・コンポステーラまで約190kmを歩いた。巡礼路の旅を経験したことで、来年はフランスの道を全ルート歩いてみたいと考えている。

ガリシアに入ってから何度か偶然再会して親しくなったのは、ドイツ出身のアーノルド(左)と息子のベン。アーノルドは仕事で日本に来たこともあり、いろいろと気遣ってくれた。ベンは途中で食べ物に当たって体調を崩していたが、歩き続けて無事に巡礼路を歩き終えた。この夏に高校を卒業して、秋からは親元を離れてダブリンで大学生活を送っている。親子ふたりでさまざまな話をしながら巡礼旅をする関係性がとても素敵に映った。

スペイン出身のアナ(右)は仲の良い夫と一緒に巡礼路を歩いていた。気さくに話かけてくれ、サリアの街まで1時間ほどを共にした。サリアで宿泊してゆっくりするというふたりに「もう少し先の街まで歩いていく」ことを伝えると、「もっとゆっくり休んでいけばいいのに!」とエールを送ってくれた。

アメリカから来たステファニー(左)とソフィーは巡礼路を歩くなかで仲良しになり、途中は別々に歩いていたが、最後の日は一緒に歩いてサンティアゴ・デ・コンポステーラに到着した。子どもの頃にコロンビアで暮らしていたというステファニーはスペイン語も堪能で、巡礼者とだけでなく現地の人と親しくコミュニケーションして、巡礼路の旅をとことん楽しんでいた。

なぜ巡礼路を歩くのか。それはBuen Caminoと一緒に旅人たちの間でよく使われた合言葉だ。その質問を受けたとき、私は20年ほど前にバックパックを背負ってアジアやヨーロッパを旅したときの話をよくした。その旅を振り返ると、そこで出会った仲間といろいろな話をし、助け合い、一緒に遊ぶなかで育まれた思い出が自分にとって原点の一つになっている。20年以上が経って多くのことが変わったが、“あの頃”と同じような経験をどこかで探している自分がいて、そんななかで思い出したのが昔から歩いてみたいと考えていたサンティアゴ巡礼路だった。
真夏の歩行は想像していた以上にきつかった。気温は30度を超え、太陽が容赦なく照りつける。それでも2週間ほど歩き続けていると、上半身と下半身の筋肉がリズミカルに連動し、足裏が地面を自然にとらえている感覚を覚え、前後に振った両腕とともに体がすっと前へ進んでいる瞬間を感じることがあった。気温は高いが、ときおり吹く涼しい風が背中を押してくれて、このままずっと歩けるような錯覚を覚えた。そんなとき、自分の将来のことや、自分がやりたいと思っていることのイメージがふっと下りてきたりする。その時間はずっとは続かないのだが、まとまった期間を歩いていると似たようなことが繰り返され、余計なものが削ぎ落とされていく感覚を持つ。
敬愛する作家、須賀敦子が『ユルスナールの靴』で歩くことについて書いている。「きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ。そう心のどこかで思いつづけ、完璧な靴に出会わなかった不幸をかこちながら、私はこれまで生きてきたような気がする」。70年近く前にイタリアへ渡った彼女にとって、欧州は今よりもずっと遠かったはずだ。さまざまな葛藤を抱えながら現地で暮らすなか、歩いて前に進んでいる時間は彼女にとってやすらぎだったのかもしれない。
巡礼路で出会った、地質リサーチのためにさまざまな場所を訪れているアメリカ、テキサス出身のアルモンドは言っていた。「世界中で多くの若者がタトゥーにはまっているのはなぜか。どう考えてもタトゥーはクレイジーだよ。でも人は一見クレイジーなことを求めている。次なるクレイジーなことは何だろうね」と。重い荷物を持ち、真夏の暑いなかをただ歩く巡礼は、少しクレイジーな行為だ。巡礼宿では同じ空間で寝泊まりするので気疲れすることも多いし、やっかいな虫に刺されることもある。でも、そんな営みに多くの人びとが魅せられ、毎日歩いていた。
大昔から人間は歩くことを続けてきた。そのシンプルな肉体的な営みは、密接に心や頭につながっていて、自分と向き合うための素晴らしい時間を提供してくれた。そして、旅や人生について似た思いを共有する多くの仲間に出会うことができた。また、自分は一人で歩いているのではなく、多くの支えがあって歩けているのだと知り、感謝の思いを持つことができた。旅の仲間、教会関係者、ボランティア、友人や家族。
巡礼路で出会った友人である韓国出身のミンと一緒に歩いていたとき、彼が救命処置について言った言葉が心に残っている。「心肺停止している人を目の前にしたとき、人工呼吸でも心臓マッサージでも、どんなことでもいい。何もやらないより、何かやったほうが絶対にいい」。彼は韓国で長く兵役を経験していて、その発言は説得力があった。同じことは、サンティアゴの巡礼路についても言えるだろう。すべての道を歩く必要はない。最後の100kmでもいいし、1日だっていい。どれだけ長く歩いたか、どれだけ早く歩いたか、そういった人と比べてどうありたいかを競う自慢大会の場所ではない。
サンティアゴの巡礼路は、自分はどうありたいのか、それぞれの歩き方を受け入れてもらえる場所なのだ。思い立ったら自分の足で一歩踏み出せばいい。そうすれば新しい旅が始まる。その先でいろんな人に出会い、大切なものを思い出し、あらたな自分を発見できるはずだ。
Profile
編集者
森川幹人(もりかわ・みきと)
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。
編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

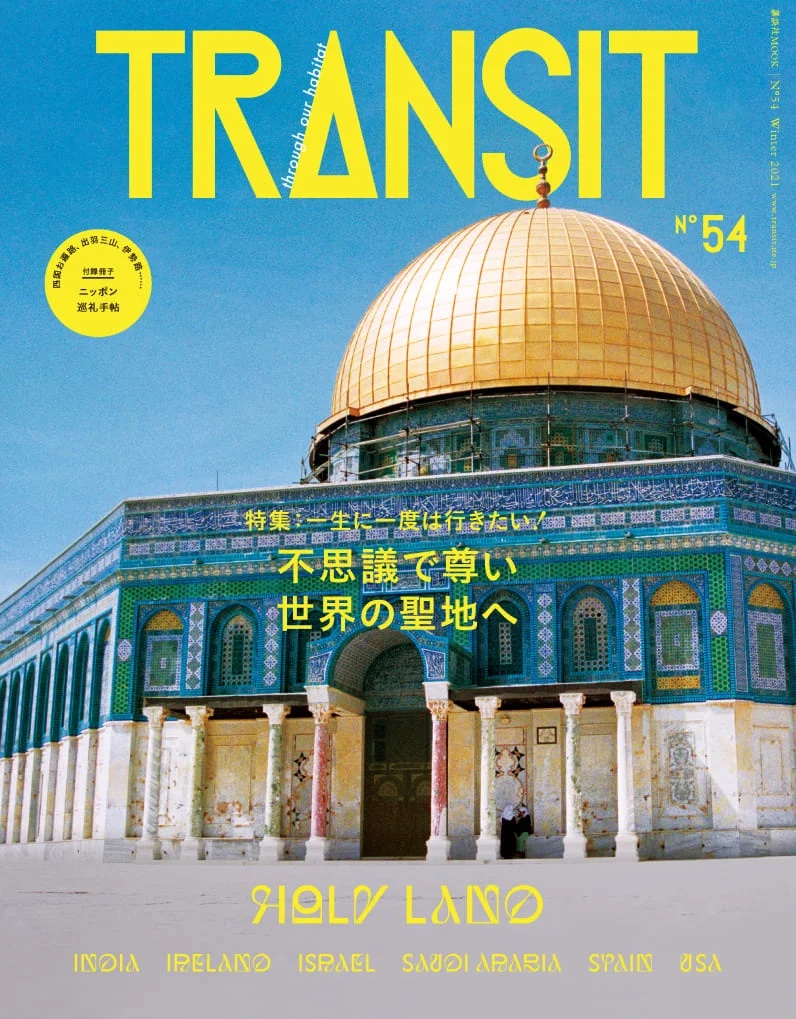









-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)






.jpg)
.jpg)
-Illustration-by-qp.jpg)























